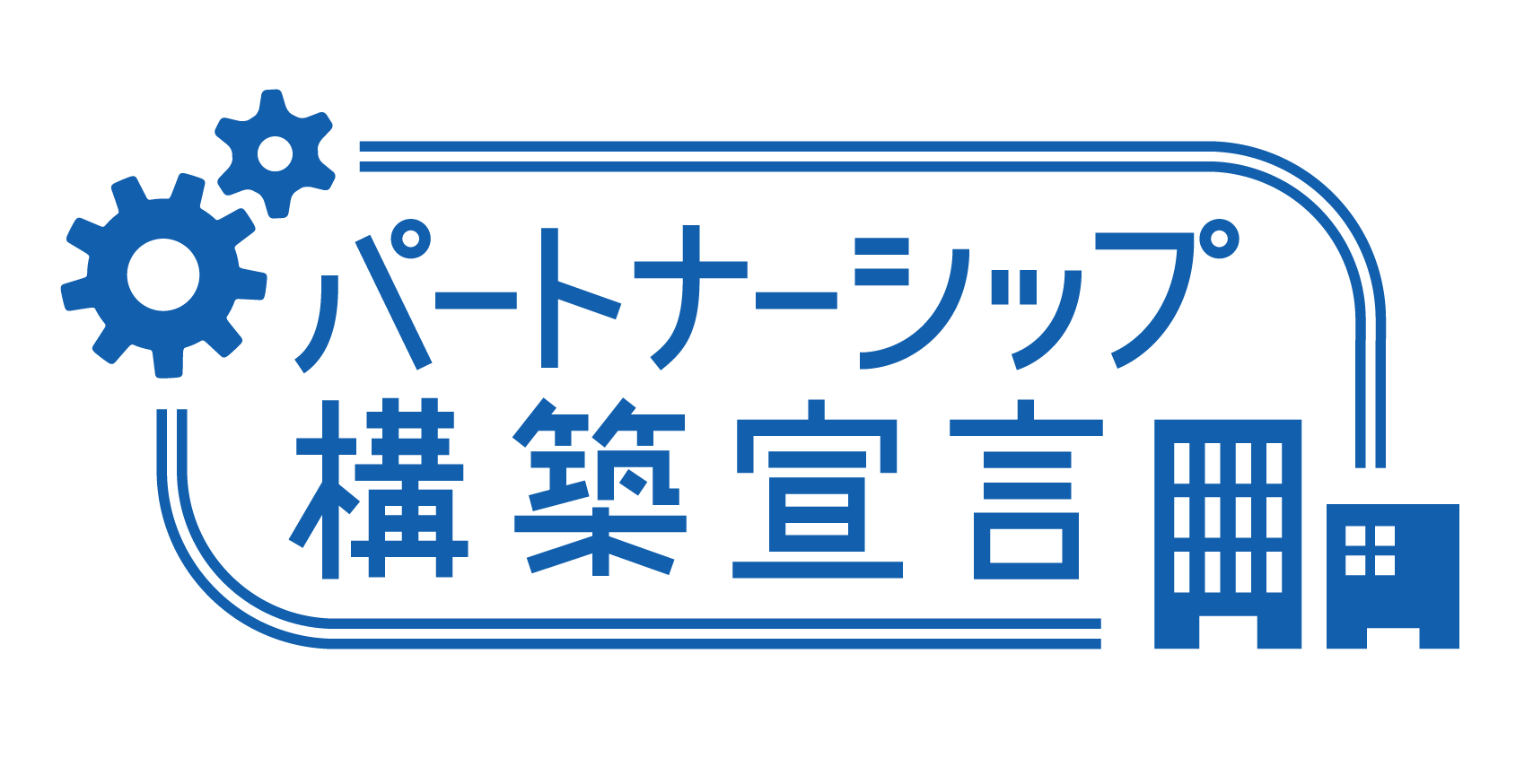[ 2013.5.31. ]
190号-2013.5.25
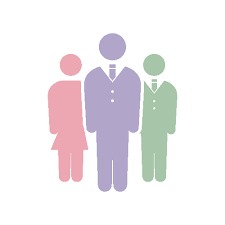
どこでも社内教育ばやりだ。 それを大きなビジネスチャンスとばかりに大手中小を問わず勧誘が多い。DMやメールが日に数十通も来る。真面目に読めばそれだけで半日は終わる。
特に不動産業界は、今いる社長以下のボードクラスが、理論的体系的教育と無縁な「やる気」「根性」だけで生き残ってきた経緯がある。「まず動け、成果は後からついてくる」という訳だ。質より量で、理由はともあれ実績で、勝てば官軍的評価で、管理職になるのも経験年数や知識ではなく、どれだけ実績を上げたかで資格が決まっていた。
入社何年目での所定の実績があれば、係長はおろか部長までも昇格した極端な会社もあった。従来の年功序列ではなく100%の成果主義だった。これが当時の右肩上がりの経済成長下では、程度の差こそあれ大手中小を問わずこの人事制度を取っていた企業が多かった。旧財閥系企業やお役所以外は例外がなかった。今では一部上場企業として存在する企業でも、かって高退職率グループに位置付けられる悪名高き企業もあった。セクハラ・パワハラは日常茶飯時、営業で実績がない社員は「月給泥棒」「ごくつぶし!」と蔑まされた。「成績を上げない社員は仕事をしていないから机や電話は不要だ!」とばかり机も取り上げられた。外に出ても経費ばかり食い、成果が上がらないから社内にいて「電話を一日200件かけろ」と受話器にテープを巻きつけられ、声をからしながら一日中顧客名簿を基に電話させられた。特に毎月の営業会議は恐怖だ。計画未達な社員は会議が終わるまで立たせられ罵倒された。「よくもまあ、抜けぬけと会社に来られるな!」「どういう性格なんだ! 親の顔を見てみたい!」と関係のない両親も巻き込まれ人間性までも否定されかねない。「お前は無能だから早く辞めろ」もっとやる気のある社員を採用するからという事だ。当時はそのやり方が、間違いなく実績に連動していたし、退職率が高くても入社する希望者は多く居た。人間追いつめられると何でもできる。
勿論、殆どの販売会社が「歩合給制」を取っていたから、給与につられて夢見た社員も多かったはずだ。そこでは「必死にノルマを追う」事が要求された。「社会も高度経済成長下に入り、社畜になる事が一生懸命さ」と受け止められた。ノルマ未達成での「病気」は理由にならない。自己管理が悪いからだと頭から否定される。「風が吹こうが、槍が降ろうが」出社してノルマをこなさなければならない。世間でも、それが「真剣さ」「真面目さ」に評価された。現代版小林多喜二の「蟹工船」だが、先進諸国へ追いつき追い越せとの国策にも合致していた。犯罪に該当しなければ何をしてもよい時代だった。「企業戦士」と一時はマスコミも持ち上げた。戦士は戦うのが使命で、上官(会社の上司)の命令は絶対だった。辞令一枚で国内は7日以内、勿論、海外までも30日以内に赴任するのが当たり前だった、さすがに海外は打診もあった。これは遠い昔の話ではない。30年前の話でそれも日本国内での話だ。
しかし、それは団塊の世代の親までが通用する価値観であり職業観であったが、その成功方程式は間違いなく夢を適えさせていた。飢えの時代を過ぎると、豊饒・成熟社会が待っていた。それに少子高齢化社会が加わると、「幸せをつかみたければ働け」から「働くことが幸せにつながらない」への根本的変化が起こった。「個性の尊重」「価値観の多様化」のもとに社会の価値観は混乱してきた。
企業組織というのは、本質的に戦闘組織である。戦う組織である以上「個人よりも団体」の論理が常に問われる。団体の名の下に個人は埋没するはずだし、そうでなければ集団的戦闘組織は維持できない。しかし、以前のような情報をコントロールし組織の都合の良い方向に向ける事が難しくなってきた。上司と部下の関係が、情報の非対称性にあった事で組織を維持できたからだ。
上司は部下よりも、経験という暗黙知を持ち、入手する情報も格段に違っていた。だから上司の判断は部下よりも、リスク回避ができ成果につながっていた。それからすれば部下は上司に判断を求めるし、尊敬も受けピラミッド型の組織が成り立っていた。組織階層が上がるほど、間違いない判断ができるようになっていた。その様なスキルを持った経営陣が判断する日本独自の「稟議制」もうまく機能していた。今日のように、あらゆる情報が瞬時にどこからでも、どこでも入手可能な社会になると、従来の組織は成り立たなくなってくるのは当然だ。上司よりも情報機器の操作に慣れた部下は、上司よりも早く情報を入手する事が出来、上司と部下の関係を維持してきた「情報の非対称性」はなくなった。その情報化社会はここ15年で到来したから、組織は混乱した。上司である管理職や経営陣も混乱した。てっとり早く「部下に迎合する」組織も出てきた。トップダウンからボトムアップの組織だ。
「三人よれば文殊の知恵」の現代版だ。従来の組織では考えられなかった現場の人の判断をくみ上げようとし、現場の人に経営者的意識を持ってもらおうとした。今はやりの現場主義だ。
企業組織内では現場に全ての解決策がある、マーケッティングでは消費者がその解答を持っているという事だ。「プロダクト思考(生産者)」からマーケッティング思考(消費者)」への転換だ。川上思考から川下思考ともいわれる。短絡的体力的営業手法からデータ重視の科学的思考は当然脚光を浴びたが、近年それも色あせてきた感がある。マスマーケッティングから個のマーケッティングが求められているからだ。成熟社会とは「すべてが行きわたった社会」で「買わなくても生きていける社会」になった事である。従来のデータや組織構築が使えなくなっている。システムや特定のビジネスモデルでは対応できなくなっている。企業も迷走し始め、やはり根底にあるのは社員教育だとたどり着いた。コンサルタントの机上の空論より、実務に抜き出た経営者が書く「ビジネス本」が売れている。㈱武蔵野の経営者の小山 昇氏、日航の再建に携わった稲盛和夫氏が好例だが、共通しているのは現場主義、競争意識、自主性をどう発揮させるか、当たり前だといわれそうな内容だ。しかしそれが出来ていないから、ナショナルフラッグと言われた日航でも経営危機に陥ったわけである。「言うは易く行うは難し」なのである。東日本大震災の対応例でも同じことが起こった。ジャーナリストの夏目幸明氏によると、NEXCO東日本は被災した常磐道を数日で復旧させたが、そこには現地事務所の迅速な対応があった。ヤマト運輸は震災直後から救援物資輸送協力隊を組織して大活躍したが、そこにはセールスドライバーたちの自主的な行動があった。それが可能になったのは同社に「全員経営」の社訓があり「手足が頭を作っていく文化」があったからだと分析している。反対なのは原発技術者たちの対応だ。個々の機器やシステムの知識や技術があるのに「誰も全体像を見ようとしていない」まずくなった時にどうするという発想がない。部分最適だが全体最適ではない。これは別名「お役所仕事」というが、事業部制、分社制でもよく起きるし、自称エリート意識を持っている社員が多い組織では要注意だ。
最近ベストセラーになっている「営業零課接待班」安藤雄介著は発想の転換と先入観念の排除、「狭小邸宅」新庄 耕著のダメ主人公は一流大学を卒業して、本文のような30年前の販売会社を彷彿とさせるところに入社して悪戦苦闘するが、「執念と継続」が必要なことを改めて認識させる。社員に一度読んでもらいたいものだ。個人を対象にした営業の原点は、「いかに顧客に好かれる」だ。「顧客にサプライズを与える」「熱い心」「顧客サイドに立った思考」だが、そこには労働法規はない、24時間考え動く事が必要だ。自分のプロポーズ相手に労働法規をとり入れたら、間違いなく「鈍感な人」「自分勝手な人」と評価され振られてしまう。
硬軟取り混ぜ、あらゆる手段を使うはずだ。本来顧客志向とはそういうものをいう。やはり個人のやる気と執念が原点だ。この辺を体現できない社員は当社の社員としては不適格だ。リーダーは早めに転職のアドバイスをした方が本人の為になる。そして人生は結婚と仕事に2度完全燃焼しなければならない。中途半端な不完全燃焼人間には誰も魅力を感じないはずだ。
社長 三戸部 啓之