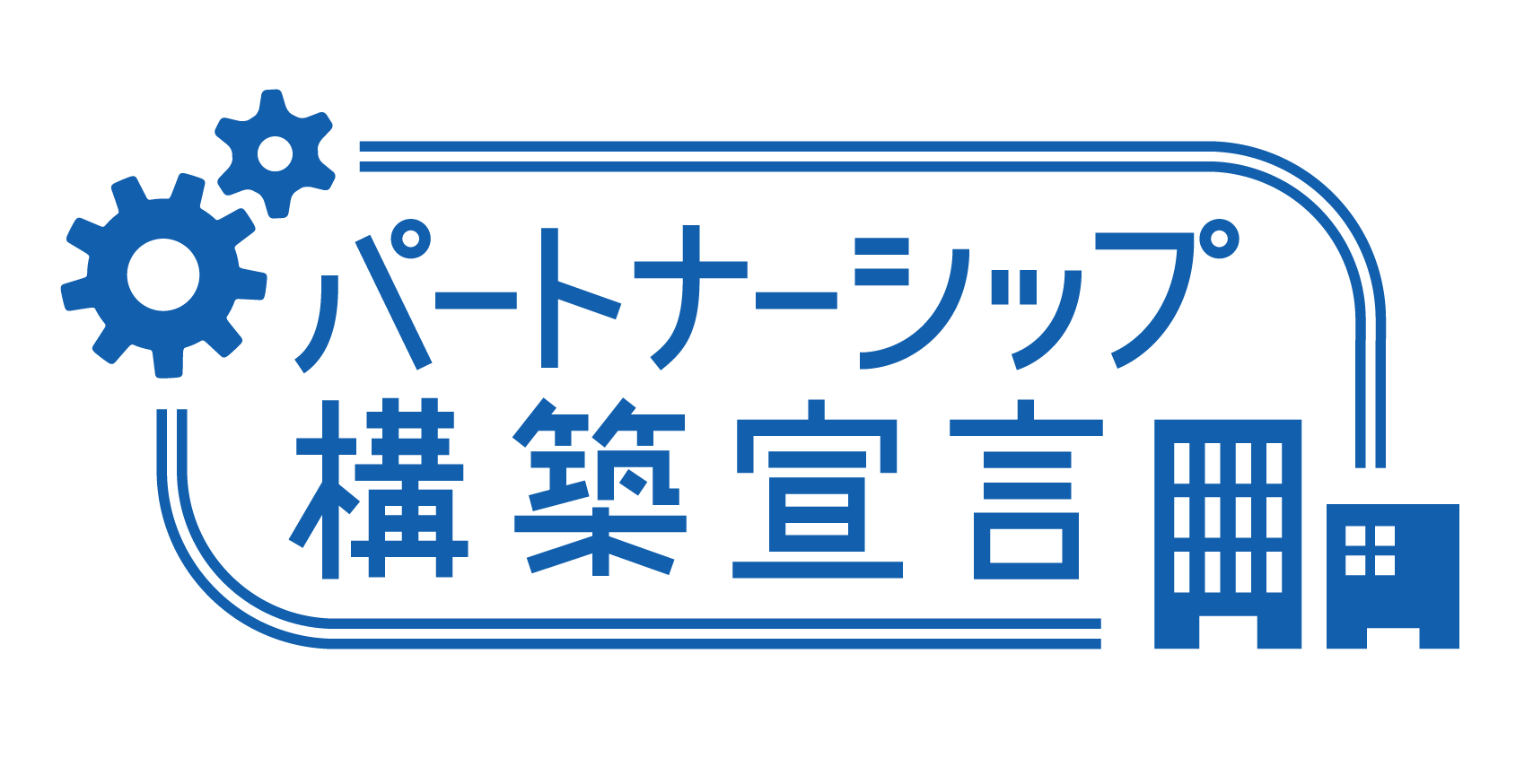[ 2019.9.1. ]
266号-2019.9.25
 基準が変わると、評価が一変するということがある。
基準が変わると、評価が一変するということがある。
私は野球に関する記事は、ほとんど見る事はないが、2018年11月13日、日経新聞のスポーツ欄に「エラーの西武!実は堅守」という記事が出ていたのに興味を惹かれて読んでみた。これによると「統計学に基づくセイバーメトリクス」という米国で開発された手法で、当社のコンサルをしていただいているH社のI社長のコラムにもあったのが以下の要旨である。
昨シーズンパリーグでリーグ優勝した西武ライオンズだが、同時に最多失策も記録していた。しかしながら大リーグでも使われている基準を基に守備力を評価すると、12球団で一番守備力が高いという評価になった。ポイントは、最多失策はエラーした数を単純に数えるのに対して、大リーグで使われている基準では守備範囲の広さも考慮に入れて評価する点にある。守備の上手な選手は守備範囲も広く、ヒットになりそうな打球にも果敢に飛びついてアウトを取ったりする。けれども、それであるがゆえに、球を取ろうとした際にエラーが生まれる可能性も広がる。
一方、守備の下手な選手は守備範囲も狭く、取れるか取れないかというギリギリの打球は最初から諦める。このため、自分の守備範囲で一定のエラーを出すものの、ヒット性の打球については、そもそも取りに行かないので、エラーが出る可能性は低くなる。
つまり、野球の守備の質を高めるという点において「狭い守備範囲で守備が下手ゆえに必然的に生まれるエラーと、広い守備範囲で守備が上手いのにやむを得ず生まれるエラー」とは区別する必要がある。単純に最多失策という基準で評価すると、両者は同じ一つのエラーとしてカウントされてしまう。これを会社の仕事に置き換えると、「簡単な仕事なのに、スキルや能力不足のために生まれる失敗と、難しい仕事でありスキルや能力があっても生まれる失敗」は、しっかり分けて評価する必要がある。
特に難しい課題に挑戦させて、上手くいかなかった時、評価の仕方を間違えると、多くの社員は失敗を恐れて、難しいことに挑戦しなくなる。そして、そういう雰囲気が社内に広がってくると、自分のできる範囲の簡単な仕事しかやらない社員が増えて、会社としての品質が上がらない。
エラーの数や事務ミスの数など、単に発生した数の多い少ないで評価するのは、評価する側も簡単だ。一方、エラーが出た時の球の飛んだ場所や事務ミスが発生した時の仕事の難易度などを勘案して評価することは、評価方法としてはより複雑になる。しかし、評価の一手間を省くことで、難しい課題には一切手を出さない失敗を恐れ、できる範囲の仕事しかしない社員が増えてしまっては元も子もない。仕事の評価方法は一度決めたら、それで終わりということは決してあり得ない。そのためには、日頃から社員の行動をよく観察する必要がある。
華麗な守備の裏には残念な失策があるように、果敢な挑戦の裏には惜しい失敗がたくさんあるはずだ。そういう意味では、惜しいし、本人も悔しい失敗と注意して大いに改めるべき失敗とを同一視してしまう。評価方法如何こそ最大の失敗を作ると言えるかもしれない。
これまでは何処でも言われる「標準的、建前」な話だ。誰も反論ができない論理だが、実際はこれが難しい。「ミスを恐れるな!」「不作為のミスより前向きのミスをせよ!」と世の経営者は声を荒げるが、評価者との信頼関係がなければ機能しない。つまり管理職と言えども、部下の一挙手一投足を見ているわけではない。目こぼしもある。部下にバイアスをかけてみる事もある。事を起こすリスクより自分の評価者としてのリスクが問題になる。仕事に難易度をつける事も意外と難しい。
組織の中では、意外と失敗やミスは後を引くものだ。レッテルを張られやすいし、捲土重来のチャンスもない。業種により加点主義より減点主義がとられるのもある。
おいしい話には群がるが、ヤバそうな話はうまくかわし、変わり身のうまい奴もいる。往々にしてその手の輩が出世する。科学的管理と言っても、営業職のように朝と晩だけ顔を合わせるだけの業務では尚更難しい。一日中、部下の仕事ぶりを監視できる内勤職に比べ困難だ。細かい注意や顧客対応も適時にアドバイスする事は難しい。だからスキルアップも個人差が出てくる。
特に営業では成果が常に問われるので、結果オーライになりやすいし、結果から日々の行動を予測する事が多くなる。自分の行動のPRが上手い社員は、成果も過大評価されやすいし、ミスがあっても叱責の度合いに差が出てくる。PRの仕方が度を過ぎると周りから見れば「嫌味」になるし「ゴマすり」にも見え「オオカミ少年」にもなる。オブラートに包んだ針小棒大的表現が、その社員の三枚目キャラと絡むと効果は抜群だ。上司から見ると「かわいい奴」になるからだ。評価の軸がそのキャラで変わってしまうのだ。天性のものという事もできる。この中ではプロセス管理は二の次になる。営業の世界に中々定着しなかったのがわかる。
一時プロセス管理という言葉が90年代実務ではやり、PDCAサイクル(plan-do-check-action)と共に、科学的管理手法として取り入れられた。しかし、本来のプロセス管理とは、成功結果を標準化する為に取り入れた手法であったが、それがKKD(勘、経験、度胸)の営業の世界に一石を投じたことは否めない。
その工程ごとにKPI(Key Performance Indicator = 重要業績評価指標)というチェック項目を設定し、進捗度を点検するものだ。鉄道線路の上をキチンと列車が走れるように見守るのだ。日本の貿易立国を裏で支えた品質管理は、その品質の良さで他のライバルメーカーを制し世界のシェアーを一気に伸ばした。
推進した日本科学技術連盟はデミング賞を作り、製造業者は、どこもかしこもデミング賞取得に血眼になった。本家のアメリカでは根付かなかったデミング賞ではあるが、ヨーロッパをはじめ品質の良さで世界市場を席巻した。そこで対抗策としてフランスをはじめとするEC諸国はISO(International Organization for Standardization国際標準化機構)規格シリーズを持ち出し、これをクリアしない製品は輸入を止める挙にでた。すると、猫も杓子もISO規格の取得に血道をあげる事になり、デミング賞は忘れられた存在になった。
平成の世になるとシックス・シグマが米モトローラで開発され、「100万回の作業を実施しても不良品の発生率を3.4回に抑える」を目指し定着していった。モトローラのシックス・シグマ開発に当たっては、日本の製造業で活発に行われているQCサークル活動を参考にしたとされる。ボトムアップ型かつ暗黙知が支配的な日本のQCサークル活動を、トップダウンで行う手法として、また統計学的な手法を取り入れた定量的評価を中心とした手法として開発された。
モトローラで考案されたシックス・シグマは、GEが経営全体のプロセス改革に適用して発展させていった。1990年代後半になって日本にも紹介され、1999年に東芝はGEの手法に習い、さらに独自の改良を加えて全社的な適用を行っているほか、ソニーでも導入されている。一時その管理手法が脚光を浴びたが、詳細すぎて現状の実務から乖離し数年で下火になり、再びPDCAサイクルが注目されたという訳だ。
組織は言うまでもなく、人間が動かしている。人間を機械のように捉えマニュアル化するのも管理手法としては効果があった。そこには生きている人間というとらえ方がない。モチベーションという考え方がないから永続性がない。承認欲求も満たされない。マスの評価ではなくきめの細かい評価ができる中小企業こそ発揮できるのではないか。これも経営トップの力量にかかっている。特に不動産業界はKKDがまかり通る世界だし、元々社員も職人的気質のものが多い。しかし、昨今はその牙城も崩れ始めている。早晩東南アジア諸国の社員も珍しくなくなるだろう。彼らにも納得できる公平な評価基準と教育が求められるのも近い。
社長 三戸部 啓之