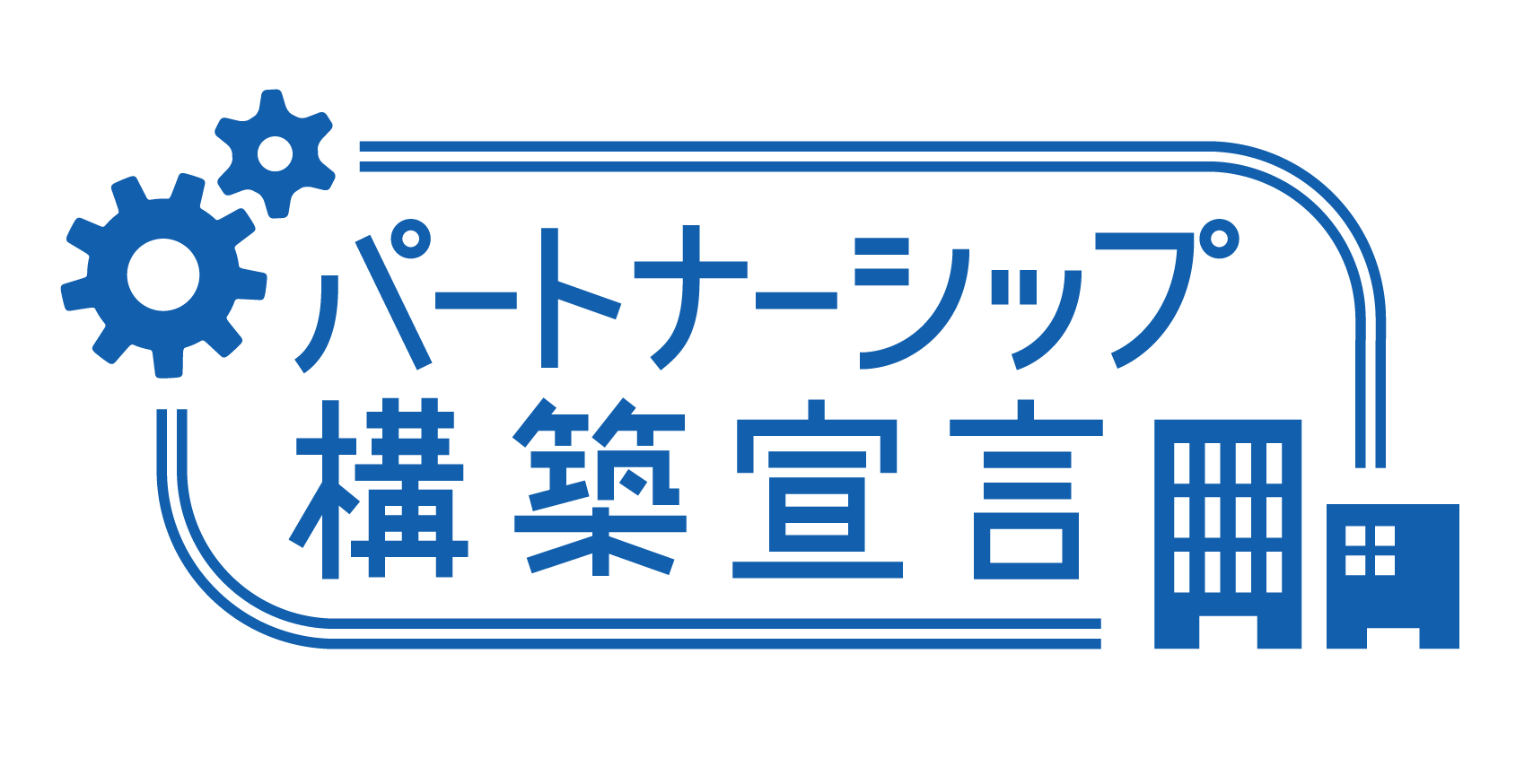[ 2021.11.1. ]
292号-2021.11
 イノベーションとチャレンジが必要と言われて久しい。企業発展の要はこの二つにかかっているという。
イノベーションとチャレンジが必要と言われて久しい。企業発展の要はこの二つにかかっているという。
イノベーションには、従来製品の改良を進める「持続的イノベーション」と、従来製品の価値を破壊して全く新しい価値を生み出す「破壊的イノベーション」があるといわれる。優良企業は、持続的イノベーションのプロセスで自社の事業を成り立たせているため、破壊的イノベーションを軽視する。
優良企業の持続的イノベーションの成果は、ある段階で顧客のニーズを超えてしまう。
自動車のモデルチェンジによる低燃費化や高性能化などにみられ、市場が成熟するにつれ、消費者が望む性能よりも企業の技術進化が常に上回るようになり、過剰供給(オーバーシューティング)が生じるというジレンマがある。結果的に、複雑で高価格な製品が市場に溢れかえってしまい、破壊的イノベーションを採る企業にシェアを明け渡すことになる。
好個の例として「iPhone」がある。携帯電話としての機能に加え、音楽プレイヤーやアプリプラットフォームなどの付加価値が付いた小型コンピューターとして開発されたApple社の主力製品だ。現在はスマートフォンとして当然のように普及しているが、あらゆるサービスを代替できる 「iPhone」の付加価値機能は、当初多くのメーカーにとって脅威となった。従来の携帯電話を「ガラパゴス化」させ、スマートフォンアプリという新しい領域の土壌をつくるなど、市場に劇的な変化をもたらしたといわれる。「iPhone」の基礎技術自体は旧電電公社(現NTT)やSONYがすでに開発していたが、あくまでも通信機能として性能追及をしていたため、顧客の利便性をとらえた商品とは考えられなかった。NTTドコモの「iモード」のように当時世界の最先端を行っていた技術もあったが、通信機能という従来製品の価値の追求であり、他の用途への開発は既存の価値を毀損してしまい、優良寡占企業は販売代理店を含めた自社の優位的地位を失ってしまう。これをイノベーションのジレンマという。
「iPhone」の付加価値機能は、当初多くのメーカーにとって脅威となった。従来の携帯電話を「ガラパゴス化」させ、スマートフォンアプリという新しい領域の土壌をつくるなど、市場に劇的な変化をもたらしたといわれる。「iPhone」の基礎技術自体は旧電電公社(現NTT)やSONYがすでに開発していたが、あくまでも通信機能として性能追及をしていたため、顧客の利便性をとらえた商品とは考えられなかった。NTTドコモの「iモード」のように当時世界の最先端を行っていた技術もあったが、通信機能という従来製品の価値の追求であり、他の用途への開発は既存の価値を毀損してしまい、優良寡占企業は販売代理店を含めた自社の優位的地位を失ってしまう。これをイノベーションのジレンマという。
馬車を何台つなげても機関車にはならないように、馬車という延長線上には機関車という発想は出てこない。発想の転換が必要だった。動力ではなく「運ぶ」という切り口が必要だった。だからこれは破壊的イノベーションになる。自動運転車や化石燃料を排し電池で走行する車を開発するのは、燃料という切り口では出てこない。近い将来、モーターを動力とした車が当たり前になり、製造するのは自動車メーカーではなく家電メーカーが家電量販店で販売したり、アマゾンのような通販会社になるだろう。従来の駆動装置で動く車は一部の趣味的購買層でそれに乗る人はマニアックな人たちだろう。今までの販売政策やガソリンスタンド等関連商品メーカーや販売店は淘汰されるに違いない。運転もコンピューターが行い運転免許制度もなくなり、スマホのような携帯端末で呼び送る事が可能になる。車を私的所有するという事も必要なく、シェアが当たり前になる。つまり車一つをとっても我々の生活は変容する。企業はこのような変化を先取りし変化させていかなければならない。言葉を変えれば、企業経営とは、下りのエスカレーターに乗って、逆向きに登っているようなものだ。立ち止まれば自分の立ち位置はどんどん下がっていく。
行きと同じスピードで上がってようやく現状維持。さらに高みにある成功と言うフロアに到達するためには、立ち止まらずに登り続けることが求められる。世界の情勢は日々刻々と変化している。ビジネスの常識も経営者を取り巻く環境も、常に変貌しアップデートされていく。そして、そうした変化は時を追うごとにそのスピードは増している。
だからこそ、企業は立ち止まったらそこでおしまいなのだ。下りエスカレーターの逆走には、転倒すると言うリスクが伴う。だから当然、足元をよく見ながら登り続ける必要がある。チャレンジする事は大事だが、そこには「するべきチャレンジ」と「してはいけないチャレンジ」があることを忘れてはいけない。
長年かけて消費者の間に定着させた本来のブランドイメージ、これは変えずに守っていかなければいけない。土台として揺るぐことのない「変えてはいけない」ブランドイメージがあってこそ、その上での変化とチャレンジが生きてくるのだ。チャレンジのスピードもポイントだ。早すぎても顧客がついてこない。まわりを見ながら半歩前進というところか。マスコミ等で一世を風靡した起業家が、数年後あっという間に影形なく消え去る事も珍しくない。それには企業の基礎体力も大事だが、鍛えるのはなかなかしんどい。子供の運動会で父兄の徒競争があるが、よく途中で足がもつれて転ぶケースを見るだろう。頭と下半身がついて来れない現象だ。これと同じく企業にも起こる。転べば企業は倒産の事態になる怖い現象だ。何時もそこで通底するのは、やはり営業力になる。かつてスーパーダイエーの創業者だった中内 㓛氏が「売り上げは全てを癒やす!」と言ったが反面真実だ。ダイエーは「価格破壊」を前面に、売り上げ至上主義を極端に追求した為、低利益、財務内容悪化で残念ながら倒産したが、中内ラッパで鼓舞された営業こそ最前線のニーズをつかむポジションにいるという指摘はいまでも十分通用する。
よく引き合いにでるのは、日清のカップヌードルだ。今では400億食が世界中で売れており、誰でも知っている大ヒット商品だ。そんなカップヌードルも実は、初めてアメリカに進出した時、全く売れなかったらしい。1973年当時、アメリカでは「カップ麺」というジャンルの食べ物自体がそもそも存在していなかったからだ。そのため、日本で大ブームになった「カップヌードル」も、アメリカ人には受け入れられなかった。日清の営業マンは、とにかくスーパーに置いてもらえるようにお願いして回ったが、「こんな変なもの、売れるはずがない…」と、結果は、全然ダメだった。
「それでも、何か方法があるはずだ」と、寝る間を惜しんで、必死に考えた結果、ある1つの「売り方 」を思いつき、藁にもすがる思いで、早速実践してみることにした。そのある売り方とは?ある言葉を追加して売った。その言葉とは、「これは具の多いスープです」という前置きトークを付けただけだ。アメリカ人にとってスープは当然、食生活に欠かせないものだった。だからその前置きトークをつけただけで、スーパーに置いてもらえて瞬く間に全米中に広まっていき今では誰もが知っている大ヒット商品になった。このように、麺という発想を変え「いかに相手に馴染みのあるコミュニケーションの方法を選択できるか?」が勝負を決めてしまうのは何でも同じだ。「念ずれば通ず!」という事だ。
イノベーションは別に有形である必要はない。松下幸之助も言う「まずは汗を出せ、汗の中から知恵を出せ、それが出来ぬものは去れ!」なのだ。当時とは時代も背景も違うので、そのまま当てはまる事はないが、企業人の本質を言っている。しかし最近では、このような言い方をストレートにすると、「パワハラ」と非難される。同じ内容でも上からの命令ではなく、本人の自覚による行動なら問題がないという。「主体性を持った自覚での行動を待つ」とは巧言だ。何人も是認するし、そうあるべきだという。だが企業経営の立場から見ると、「何時までに」という納期がないのだ。ビジネスで納期がない事はあり得ない。全てが納期を前提に動いているからだ。それは信用にもつながり企業の存立につながる。
「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」徳川家康「鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス」織田信長「鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス」豊臣秀吉と言われるが、企業サイドから言えば、家康の言葉は難しい。納期を考えた行動の心的動機付けは「利益」と「強制」しかない。一方の強調だけでは組織は機能しないが、この使い分けがポイントだ。組織リーダーの必須条件になった。
会長 三戸部 啓之