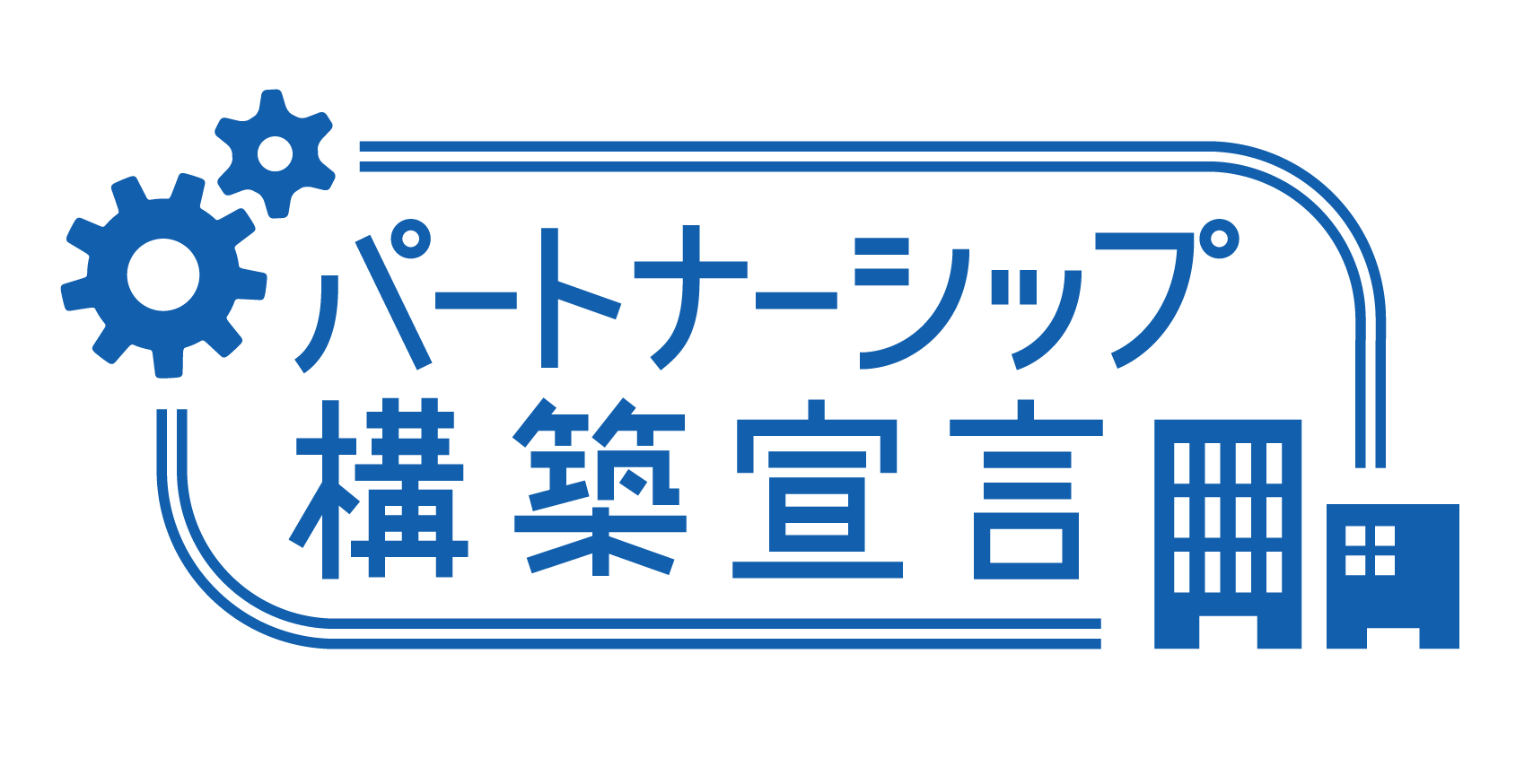[ 2022.10.1. ]
303号-2022. 10
1970年代後半~80年代、深刻な社会問題として取りざたされたのが、不登校児童、生徒の急増だった。その原因には様々なものがあるが、その背景には濃厚な母子密着があり、更にその背後には父親の心理的不在があるとされた。その当時から、不登校問題に限らず、父親の働き過ぎ、それによる家庭での存在感の薄さは好ましくないと指摘されていた。そこで唱えられたのは「父親の復権」だった。
母親が子育てをするのが当たり前のようになったのは、専業主婦と言う形態が一般の人々の間に普及してからだと考えられている。専業主婦と言うのは、夫の収入だけで生計が成り立たない限り成立しない存在で、特に裕福な家庭においての一つの妻のあり方と言える。そのような専業主婦層から、子供の教育に熱心な母親達が現れてきた。教育評論家の小嶋秀夫氏によると「教育者としての母親」の役割が日本の社会の中で実質的な意味を持ち、目に見える形に働き始めたのは明治から大正時代にかけてのことだとされている。それは日本の産業革命も一段落して資本主義が成熟段階に達して都市中間層と呼ばれる人々を中心に中等、高等教育への進学志向が高まり、現在と本質的に同じ教育熱心な母親が現れた時だと言う。子供の教育機能を担う学校制度が整うにつれて、そうした流れに変化が生じてくる。つまり学校における義務教育の普及により、子供の教育は次第に学校任せになって行き、母親が担う子育ての機能は身の回りの世話に縮小されていった。それに核家族化により、舅や姑がいなくなれば家庭内の配分権は父親から母親に移らざるを得ない。まして働き過ぎで家に居ない父親と給与が銀行振り込みとなれば、その配分は母親の主導にならざるを得ない。家電製品が行き渡り、家事に費やす時間が減ると、母親の関心は子供と自分自身の消費に向かう。母親の父親に対する期待感は薄れ、以前とは違う性別役割分業が起こったのだ。
少子化社会になると状況は一変し、子供への期待感はさらに強まる。
学歴社会が浸透すると、高学歴志向が強まる。幼児教育→有名幼稚園→有名小学校、中学→高偏差値高校→有名大学→有名大企業への路線が一般化する。これは1970年代までの右肩上がりの高度経済成長期までは妥当な選択だった。本来は日米安保協定の中で日本の立ち位置の説明だった中曽根元首相の「不沈空母」発言に端を発し、銀行をはじめ財閥系企業を中心とした有名大企業を目指すようになった。難関ではあるが入社さえすれば福利厚生をはじめ定年まで安定した生活が保障されたのだ。
当然、母親としてはわが子を当該有名企業に入社させるために、あらゆる資源を投入することになる。まして少子化で子供一人にかける時間や資源は多くなり、「教育ママ化」は必然的に起こる。建前上、世帯主である父親も「教育ママ」を後押しする事になり、子供を追い詰める。当時父親の復権が唱えられたが、通勤地獄と揶揄される往復3時間と競争社会の中で酷使されヘトヘトになった父親にもう威厳はないし、そんな父親に対して尊厳もなくなる。家庭の中に緩衝材や逃げ場がなくなり、子供はますます孤立化する。それが先の「不登校問題」や「鬱や家庭内暴力」につながり社会問題になった。悪者探しで父親に責任を転嫁されてはたまらない。教育は公共性があり社会的責任である。
さらに「いい子症候群」も問題になっていた。それは、素直で真面目な良い子が有する、目立ちたくない、理想は均等分配、自分では決められない、周りから浮くことばかり気になる、安定した仕事を優先し、主体性の要求されないお膳立てされた社会貢献には関心がある、などの行動原則をとる子供たちだ。
金沢大学教授の金間大介氏によると、これを見出したのは大人ではないかと指摘している。
『挑戦が成長につながることを実感できないのは大人であり、一度失敗すると這い上がれないと思っているのも大人であり、既得権信者もやはり大人である。それが子供たち若者たちに空気感染する。もちろん若者自身も、空気の同調圧力はそれを増幅する役割の人が登場することで決定的になる。』
しかし、根強い学歴信仰もコロナ禍で激変した。
ここ数年、日本企業の間では事業構造改革の動きが生まれており、コロナ禍と言う黒船によって一気に表面化した。3つの変革、脱炭素、デジタル化、事業再編、への意欲が高まっている。特に脱炭素への取り組みは日本企業の低消費電力技術、電動化技術との親和性が高い。もう一つの大波はデジタル化だ。2014年は団塊の世代が65歳になって大量に退職した年で、デジタル化による省人化が促された。人手不足を背景に女性の社会進出が進み、共稼ぎ世帯が増えて電子商取引も普及した。コロナ禍によって経済や社会の構造が連続的に変わってしまったため、それに適応する事業再編も当然に求められた。リモートワークが進み、出社を前提とした就労環境が変わってきた。通信手段を伴う間接的な業務処理が求められ、指示に即応する成果が求められるようになった。
従来の年功序列型賃金体系ではなく成果型報酬体系に変わってきた。
高学歴=成果ではなく、スキル=成果になったのだ。もちろん有名難関大学=成果は一部ではあてはまるが、その尺度では採用にも失敗が多くなる。
しかも、「いい子症候群」にとらわれた「有名難関大学卒」の鬱罹患率も高く企業の採用戦略の見直しにつながった。下手に採用して、ブラック企業の烙印を押されでもしたら取り返しがつかないからだ。またその手の学生は退職にすぐ結びつくので、企業側の採用コストもばかにならない。そのような背景もあり、今まで批判の多かった成果型報酬制度と職務記述型雇用(JOB型)が出てきたわけだ。
従来だと大卒社員は、総合職として各部署を2-3年で動きサラリーマンすごろくとしてゴールが課長部長に、同期でとびぬけた一名だけが社長になる厳しい生存競争の勝者であった。この雇用システムこそが日本社会の国富低迷の元凶とされた。
有名な逸話がある。定年者の再雇用面接で面接官が「あなたは何ができます?」と聞かれ、「私は部長ができます」「私は決済ができます」と答えた事に、欧米諸国では考えられないほど驚きをもって伝えられた。企業が求める職務で応募する以上、職務記述書により採用されるわけで、それができるか否かが採用条件となり、学歴や年齢、性別は一切関係がない。同一職務同一賃金は安倍首相の言葉ではなく世界標準なのだ。日本では、「どこにお勤めですか?」と聞かれると「〇〇会社に勤めています」ということが一般的だが、欧米では「経理を担当しています」とか、「販売促進を担当しています」とかいうのが当たり前で、会社に所属している点は関係がないとされる。欧米では会社に勤めるということは自分のキャリアアップのための手段であり、その職務の専門家になることを主眼としているから、常にスキルアップを図るために転職をすることになる。日本のように数年で他部署に異動することになれば社員からクレームが来て退社してしまう。だからと言って日本人は会社に愛着を持っているのかというと60%の社員が不満を持っており、欧米諸国と差がないという。その原因は色々と取りざたされているが、年功序列制度が希薄になったとか終身雇用制度がなくなったとか言われているがどれも当てはまらない。元々年功序列はあった筈で、官僚や旧軍隊だけで年次序列があったに過ぎない。終身雇用制度も少子化による労働人口減少に伴い定年延長が実施されているし、新卒一括採用や職務を問わない採用制度も若者の失業率低下に寄与している。欧米諸国で若者の失業率が高いのは、企業の求めるスキルがないから当たり前だし、企業側が若者から解雇するのも、うなずける。今の若者の軟弱さを憂いて短兵急に成果型報酬制度を導入するのもメリット、デメリットを良く考える必要がある。
ここで間違いなく、少子高齢化を踏まえて日本は「移民国家」になるであろう。出入国在留管理庁による在留外国人総計では、2012年12月全国で203万人、首都圏では78万人の外国人がいたが、2020年12月では夫々292万人、首都圏では116万人になっている。全国では143.8%増、首都圏では148.7%増で技能実習1号、2号総計でも15万人から39万人と260%の増加だ。これらの人々が規制緩和の中で我々の労働市場に入ることは、軟弱な日本人の勤務する場所がなくなることを意味している。
会長 三戸部 啓之