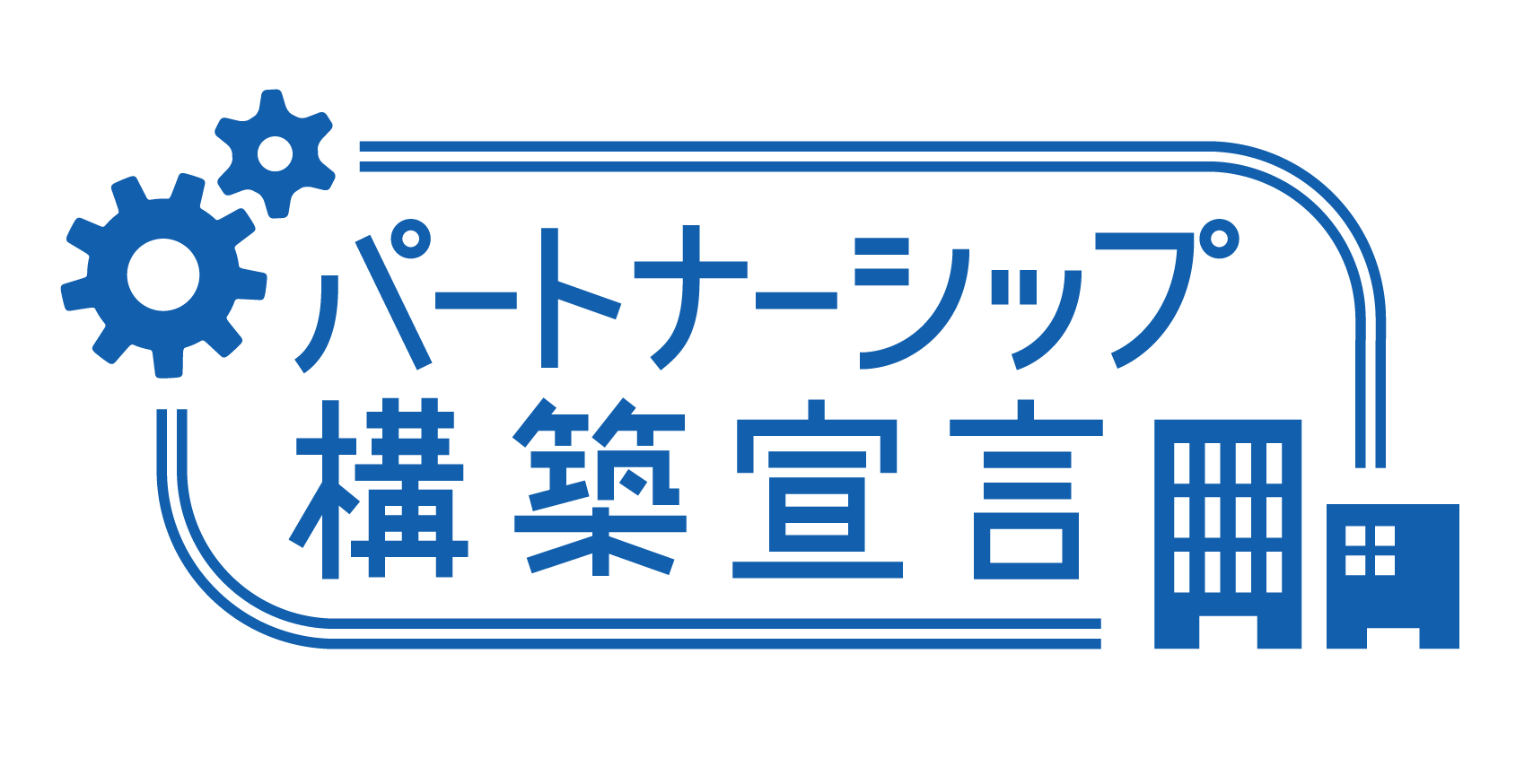[ 2024.7.1. ]
324号-2024. 7
 「会社の規模は大きい方がいい」「ビジネスは大企業の方が有利」と、考えていないか?その考え方が、自分の事業・会社の成長を妨げている可能性があるとしたら...?成長志向は非常に重要だが、行き過ぎた成長志向は逆の結果に繋がる可能性がある。
「会社の規模は大きい方がいい」「ビジネスは大企業の方が有利」と、考えていないか?その考え方が、自分の事業・会社の成長を妨げている可能性があるとしたら...?成長志向は非常に重要だが、行き過ぎた成長志向は逆の結果に繋がる可能性がある。
ソニー創業者である井深大氏は、1976年に次のように述ベている。「従来の成長志向から早く転換に成功した企業が勝つ」
この発言の後、日本はバブルとなりジャパン・アズ・ナンバーワンと呼ばれる時代を迎えるわけだが、その遥か前から井深氏は世の中の成長志向に警鐘を鳴らしていた。
さらに次のように語っている。
「これからの経済成長はたしかに平均点では伸びが鈍化する。しかし、伸びる企業はうんと伸びるし伸びない企業はこれまでよりうんと悪くなって優劣の差が非常にはっきりする というのが私の考えです。そこで伸びるのは平均的な考え方から離れて、どこかに特殊性を求めるというはっきりしたポリシーを持って運用される企業ですね。よその真似をして平均的になんでもかんでもそろえていこうなんてやり方は非常に辛くなりましょうね。」
そして、今後の企業経営を次のように予想した。「これからは大企業のスケールメリット(規模の利益)が、メリットでなくなっていくような気がします。本当のスペシャリティを持った企業が伸びていく時代ですよ。事実、37人の従業員で技術だけを売って年間60億円を売り上げている光学会社とか、アルミサッシの表面処理剤を売って127人の従業員で90億円の収入をあげている化学会社なんかが、現に立派にあるんですからね。」
『規模を求めるのではなく、本当のスペシャリティ(専門性)を求めよ』
『スケールメリットは失われていく』など1970年代のメッセージでありながら現代にも通じるメッセージの数々といえる。
「確かにそうだ」と、うなずく気持ちもあれば「既に専門性はあるけど、売上はあまり...」「どう専門性を高めればいいかわからない...」と心の声が沸き起こるかもしれない。
なぜ、専門性だけでは売上に繋がらないのか。そこには、成長志向だからこそ見落とさせる重要な「秘訣」があるらしい。その「秘訣」を知ることで、自社の利益だけでなくお客さまも、より幸せになり協力企業にも喜ばれ、お客さま、協力企業、自社の三方の利益を生み出せる。
高度成長経済下では、大量生産大量消費が前提になるので、品質と価格がポイントになる。しかし、低成長経済になると必需品は万遍なくいきわたり、欲しいものがなくなる。そこで欲しがるものを作る必要がある。
第一段階として希少性がある。他人が持っていないものを所有する事が自分の記号になり差別化要因となる。価格の設定も高額化が可能だ。シャネル、ヴィトンやディオール等原価の数十倍の価格だが、女性の垂涎の的だ。使用・品質価値は数万だが所有価値が100万単位になっている。これがブランド=記号消費というものだ。
第二段階として「モノ消費からコト消費」になると、モノの物語性が必要となってくる。その物語性が所有の正当性をアピールできるからだ。
成長志向とは「明日は今日より良くなる」単線思考だともいえる。有為な専門性を持っている企業ほど唯我独尊の陥穽(かんせい)に陥りやすい。マーケットが見えない自己陶酔型思考といえる。運よく市場に合致すれば成功するが、「後先見ずの猪武者」になりやすい。とはいえ成長志向は企業経営者にとって必要な素質である。
このハードルを乗り越えた企業には必ず名参謀・女房役がいる。本田宗一郎氏には藤沢武夫氏がいたし、ソニーの井深大氏には盛田昭夫氏がいた。豊臣秀吉には豊臣秀長がいたし、徳川家康には 謀臣の本多正信がいた。石田三成のような能吏は組織には必要だが、私企業の方向性を担う参謀役は少ない。企業経営者たるものこの参謀をいかに自分のそばに抱えるかが、企業の命運を占うといっても過言ではない。街場の中小企業や商店でもこの女房役が機能している処はリーマンショック後の不況期でも健全な経営を続けている。女房役と二人三脚をできる度量が相手には必要だがミスマッチも多い。茫洋とした主人に利発な奥さん、愛想のいい奥さんなんかは好例だ。駿馬はいても名伯楽がいなければ、宝の持ち腐れになってしまう。
先達企業の例を持ち出すまでもなく、中小企業ではタイトロープ経営をせざるを得ない状況から、経営者は名伯楽(参謀)をいかにそばに置けるかにかかっている。苦言を言ってくれる役員や社員が必要だ。それを許容するトップの姿勢が企業を盤石にする。
成長志向の陥穽には、守備範囲を広げすぎるというものがある。経営資源には限界があるのにかかわらず投資先を広げる危険性だ。80年前の旧日本軍の過ちが好例だ。つまり一つはロジステックの問題だ。戦国時代の戦い方は、武器兵糧を運ぶ荷駄部隊が戦闘部隊の後4キロも続いたそうだ。織田信長からは専門の戦闘部隊を設立したが、それまでは農民を主体とした戦闘部隊で農繁期は戦いを避けていたし、農民の反感を買うような現地調達はしなかった。ところが昭和の軍隊はロジステックの観念は軽視し現地調達が主体となったため、戦地の人々の反感を買いゲリラ化し日本軍を苦しめた。輜重部隊は部内では兵隊以下とみられていたし、指揮官も砲術科、歩兵科出身より軽視された組織上の問題もあった。勿論現地では略奪もあったろうが、基本的に軍票での支払いを行ったが、その軍隊が敗退すれば、ただの紙切れになったので、現地では意味のないものと判断された。
東南アジアで日本の評判が悪いのは人権軽視とこの軍政の失敗が大きい。企業におけるロジステックは資金供給と人的供給だが、これをシビアに点検しないと単なる一発勝負になり永続性の保証はできない。経営資源の限られている中小企業は、異業種進出や過剰投資は命取りになりやすい。
もう一つは、周りからの甘言だ。「社長という名詞」の効力はマダマダ大きい。規模の大きさにかかわらず、名刺は肩書だからだ。組織を代表するという優越性が「あら、社長さん」という相手からの指呼が自尊心をくすぐる。経営者が実感できるのは、周りからの阿諛追従(あゆついしょう)の言葉と高い給料で可能になった贅沢のもたらす「束の間の気持ちよさ」だけだが、より自分の立ち位置を主張しようとすると、売り上げ至上主義に陥り過大投資に向かってしまう危険性がある。遊びを知らず真面目な経営者こそ陥りやすい罠だといえる。
特に2代目は創業者を最大のライバルとするから、社内的なアドバンテージを確保するためにもこの罠に陥りやすい。1986年~1991年のバブルに踊った経営者の死屍累々がその証拠だ。「土地神話」がそれを後押しした。財テクという名の金融機関からのアプローチも加わった。日本国民が酩酊状態になっていた。「今日より明日はもっと良くなる」という根拠のないムードに浸っていた。それが奈落の底に向かう悪魔の案内だったという事もわからなかった。
「消費は美徳」だといわれ政府も音頭を取った。マスコミも扇動した空気の中では独自の路線を貫くことは難しい。ポストバブル30年で貴重な経験者がいなくなっている令和の今日、また同じようなバブル期を超える株価が国内を覆っている。歴史は繰り返す。同じ過ちを繰り返さないように心すべきかもしれない。
会長 三戸部 啓之