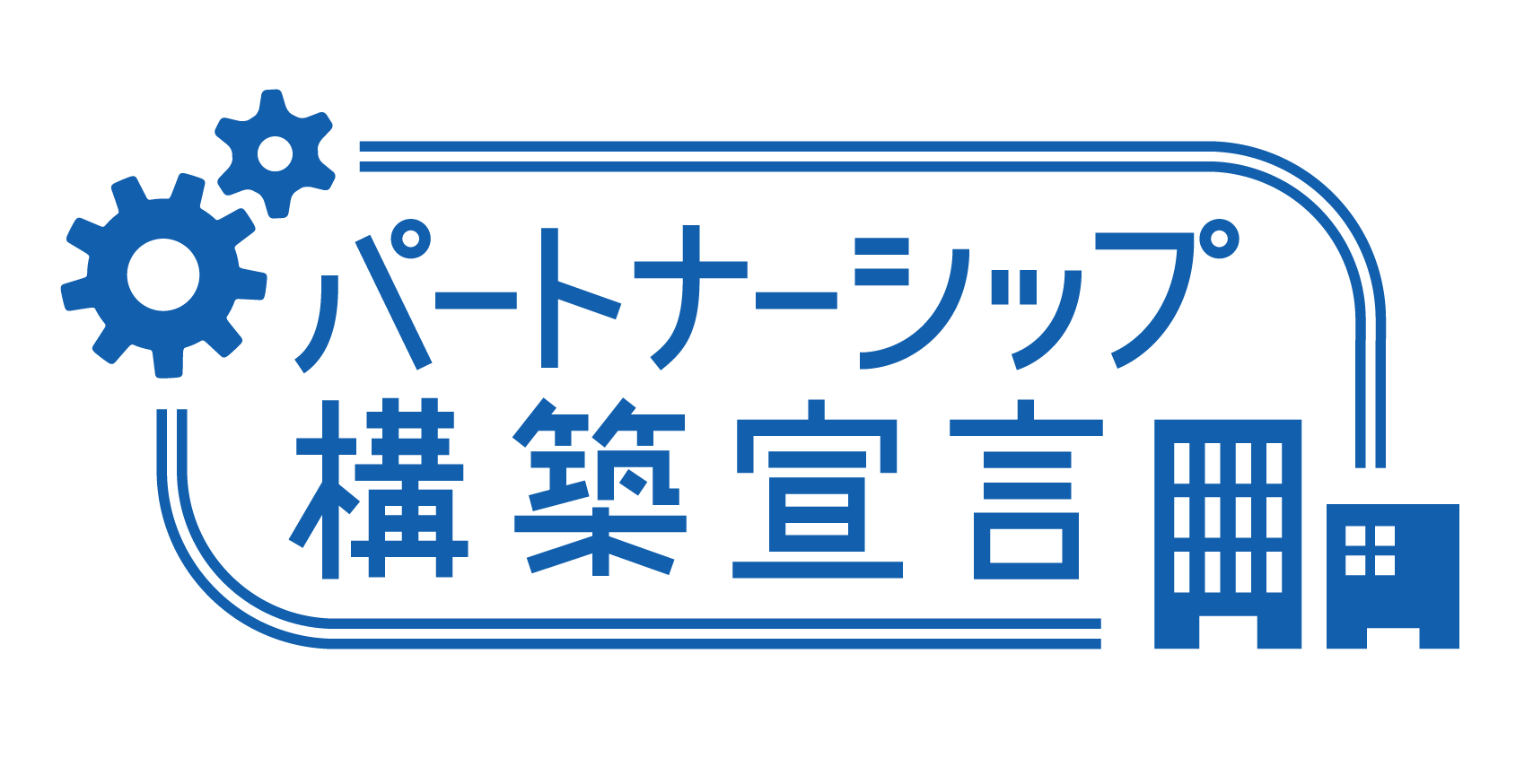[ 2024.9.1. ]
326号-2024. 9
 爽快なレモンの香りとシュワッとはじける炭酸「ハイボール」、健康志向の風潮を受けて最近の人気商品らしい。当社でも懇親会などで若い社員を中心に、一回はハイボールをオーダーする。実は、このハイボール。「角瓶」でも有名なサントリーが生み出した商品だといわれる。
爽快なレモンの香りとシュワッとはじける炭酸「ハイボール」、健康志向の風潮を受けて最近の人気商品らしい。当社でも懇親会などで若い社員を中心に、一回はハイボールをオーダーする。実は、このハイボール。「角瓶」でも有名なサントリーが生み出した商品だといわれる。
サントリーがハイボールを生み出したのは、ウイスキー市場が底をついた2008年だという。サントリーはどのようにしてハイボールを生み出し、お酒の定番にのし上げたのか、興味をそそる。
元来ウイスキーは我々世代からすると「渋いオヤジが飲んでいる」というイメージがある。映画でもバーカウンターのシーンではビールではなくウイスキーが定番だ。ビールやカクテルでは渋いオヤジにそぐわない。以前は洋酒と呼ばれ、字も「ウヰスキー」と表示されていた。戦前、洋酒は上流階級しか飲めない高級品だったし、庶民にはハレの日しか飲めない贅沢品だった。戦後もしばらくは海外旅行の土産として、洋モク(欧米のタバコ)やジョニーウォーカー黒ラベルなんかは、定番だったし喜ばれたものだ。戦後は洋風化が促進され一般家庭でも普及し始めたが、鳥井信治郎(サントリー)と竹鶴政孝(ニッカ)はジャパニーズ・ウイスキーの普及に貢献したことは間違いがない。
ウイスキー市場は1983年をピークに成長を続け、その時のイメージこそ「渋いオヤジが飲んでいる」だった。実際に、銀座や六本木でボトルキープをするのがステータスになっていたらしい。映画でも渋いイケメンのオヤジが、バーカウンターで一人ウイスキーを飲んでいるシーンは格好が良いものだった。そこに絶世の美女がすり寄ってきたり、美女に目配せして杯を重ねるなんて、本当に絵になった。酒と美女の組み合わせは小説の世界でも映画の世界でも定番となった。
以前の専売公社(現JT)の「タバコは動くアクセサリー」なんてテレビCMが頻繁に流されたが、タバコの紫煙とウイスキーは相性のいい小道具だった。大人を醸し出す記号でもあったから、当時の青少年は違反とは知りながらマネをしたものだ。ちょっと生意気な高校生のイニシエーションにもなった。1965年ごろは、まだ繁華街でも浮浪者がシケモク(吸い残したタバコを拾って吸う)を吸うほどだったし、ゴールデンバットという不味い国産たばこも先を争って買っていたものだ。国産たばこは低品質だったため、洋モクが羨望の元になったわけだ。しかし、バブル崩壊から続く不況により、渋いオヤジの消費は落ち込み市場は縮小しだした。そして、消費量が底をついた2008年、サントリーが打ち出したものこそ「ハイボール」だった。
もしかすると団塊の世代は「ハイボールはじめました。」というサントリー角瓶の広告を覚えているかもしれない。当時はやった「トリスを飲んでハワイに行こう!」なんてCMが茶の間に流れ、「憧れのハワイ旅行」として一般国民の夢を誘った。当時ハワイは芸能人や富裕層の行く場所であり遥か夢の世界だった。経済成長とともにトリスから角と変わったが、ビンも手の込んだ薩摩切子にヒントを得た亀甲模様のボトルデザインが特徴になった。ハイボールの元祖であるトリスウイスキーのTV広告は独特のトリスおじさん(アンクル・トリス)が、街のあちこちにあったトリスバーでうまそうに飲むシーンが印象的だったはずだ。アニメの広告キャラクターとして1958年~1981年まで珍しく長寿を全うした。なぜ、サントリーは角ハイボールを打ち出したのか。
その秘密は「ターゲットの変更」にあった。消費が底をついた2008年サントリーは「30代のサラリーマンがウイスキーのソーダ割を飲んでいる」という情報をキャッチする。シニア層の消費は回復していなかったが30代の消費は回復しつつあった。
市場調査の結果、ビールよりも安く水割りよりも飲みやすい。つまり「リーズナブルに軽く飲めて酔える」というニーズをウイスキーのソーダ割は満たしていた。しかも、低糖質、カロリーも控えめで、今の健康志向ブームに合致している。
そこでサントリーはハイボールを商品化し、30代向けにキャンペーンを実施、大ヒットになった。又2010年代に、日本ウイスキーの歴史を扱った連続テレビ小説『マッサン』が大ヒットした事もブームを後押しした。勿論、ただ「ターゲットの変更」をすれば成果が出る訳ではない。
サントリーは
〇 ターゲット変更、 〇 売れるための市場調査、 〇 「リーズナブルに酔える」という顧客の本当のニーズの把握、 〇 秀逸な宣伝手法とイメージキャラクターの登場
これらのマーケティング施策を、正しく実践できたからこそV字回復させることができた。これらは、すべて異なるマーケティングの知識と言われ、「マーケティングミックス」をビジネスに応用した。当時のサントリー宣伝部は、伝統的に開高健他有能な宣伝マンやコピーライターが多く在籍していた。これに相当する宣伝部の設立は、我々中小企業には無理だが、これを当社に置き換えてみれば「売れるための市場調査:空室をいかに減らすか」「ターゲットの変更:リノベーション」「リーズナブルに酔える:快適な住空間の提供」になる。これらは管理会社として自称するなら当然日常業務として行動しているはずだ。難しい横文字を使わなくても、顧客の立場に立てば発展思考として出てくる。我々の不動産業界は、そもそもマーケットという発想自体がなかった。供給不足の市場では消費者という概念が不要だった。不動産という代替えのない商品を仲介販売する以上商品知識もあまり必要ではなかった。説明もないまま「現況有姿」の記載で事足りた時期もあった。顧客志向もなく「気に入ったら買えば?」「気に入ったら借りたら?」というレベルでビジネスが成り立っていた。勿論商品説明を事細かに求める客は面倒な客で忌避したりしていたから、業界に携わる社員もKKD(勘・経験・度胸)で十分だった。土地神話に裏付けられた不動産業界は、毎年地価が上昇していたから、契約誘因は単純話法で事足り、社員の業務スキルは必要なく、殿様商売ができた。街の不動産屋で土地仲介を数件やれば一年間食べていけた時代があった。しかし、アフターコロナで業界は激変した。
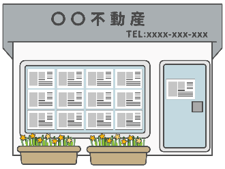 非対面でITを駆使する事が当然となり賃貸不動産管理業界にも法規制が厳しくなり、業者の淘汰につながってきた。帝国データバンクのデータによれば不動産事業者数は平成21年から平成26年で126.582社から122.631社(▼3.7%)となっている。原因は不況型倒産と後継者問題である。一般的に不況型倒産とは「売れない・買わない」が原因で売り上げが低迷し倒産に至るのだが、街の不動産屋ではよほどの無理をしない限り不況型倒産はない。売る前提となるマーケティング志向は初めからないし、まして顧客志向なんて鼻からなかった、待ちの営業で十分だった。たまたま運よく土地の仲介や売買が入れば成り立つ「ヤクザな商売」だった。業界平均企業の従業員の95%が5人未満という中では、経費もかからず企業組織という概念自体あり得ないから、やっていけた。江戸時代から続いた「口入れ屋」「差配人」が起源と言われるが、同じダーティーなイメージがあった金貸し(金融)は、明治期の殖産興業の掛け声とともに高額な給与で帝国大学生を採用し業界のレベルアップを図ったが、不動産業界は後れを取り現在に至ったわけだ。しかし、アフターコロナ後の不動産業界の変容は目をみはるばかりだ。社員のレベルアップと企業としての矜持がある組織しか生き残れないだろう。
非対面でITを駆使する事が当然となり賃貸不動産管理業界にも法規制が厳しくなり、業者の淘汰につながってきた。帝国データバンクのデータによれば不動産事業者数は平成21年から平成26年で126.582社から122.631社(▼3.7%)となっている。原因は不況型倒産と後継者問題である。一般的に不況型倒産とは「売れない・買わない」が原因で売り上げが低迷し倒産に至るのだが、街の不動産屋ではよほどの無理をしない限り不況型倒産はない。売る前提となるマーケティング志向は初めからないし、まして顧客志向なんて鼻からなかった、待ちの営業で十分だった。たまたま運よく土地の仲介や売買が入れば成り立つ「ヤクザな商売」だった。業界平均企業の従業員の95%が5人未満という中では、経費もかからず企業組織という概念自体あり得ないから、やっていけた。江戸時代から続いた「口入れ屋」「差配人」が起源と言われるが、同じダーティーなイメージがあった金貸し(金融)は、明治期の殖産興業の掛け声とともに高額な給与で帝国大学生を採用し業界のレベルアップを図ったが、不動産業界は後れを取り現在に至ったわけだ。しかし、アフターコロナ後の不動産業界の変容は目をみはるばかりだ。社員のレベルアップと企業としての矜持がある組織しか生き残れないだろう。
アーバン企画開発 相談役 / ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之