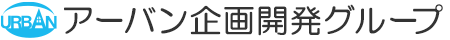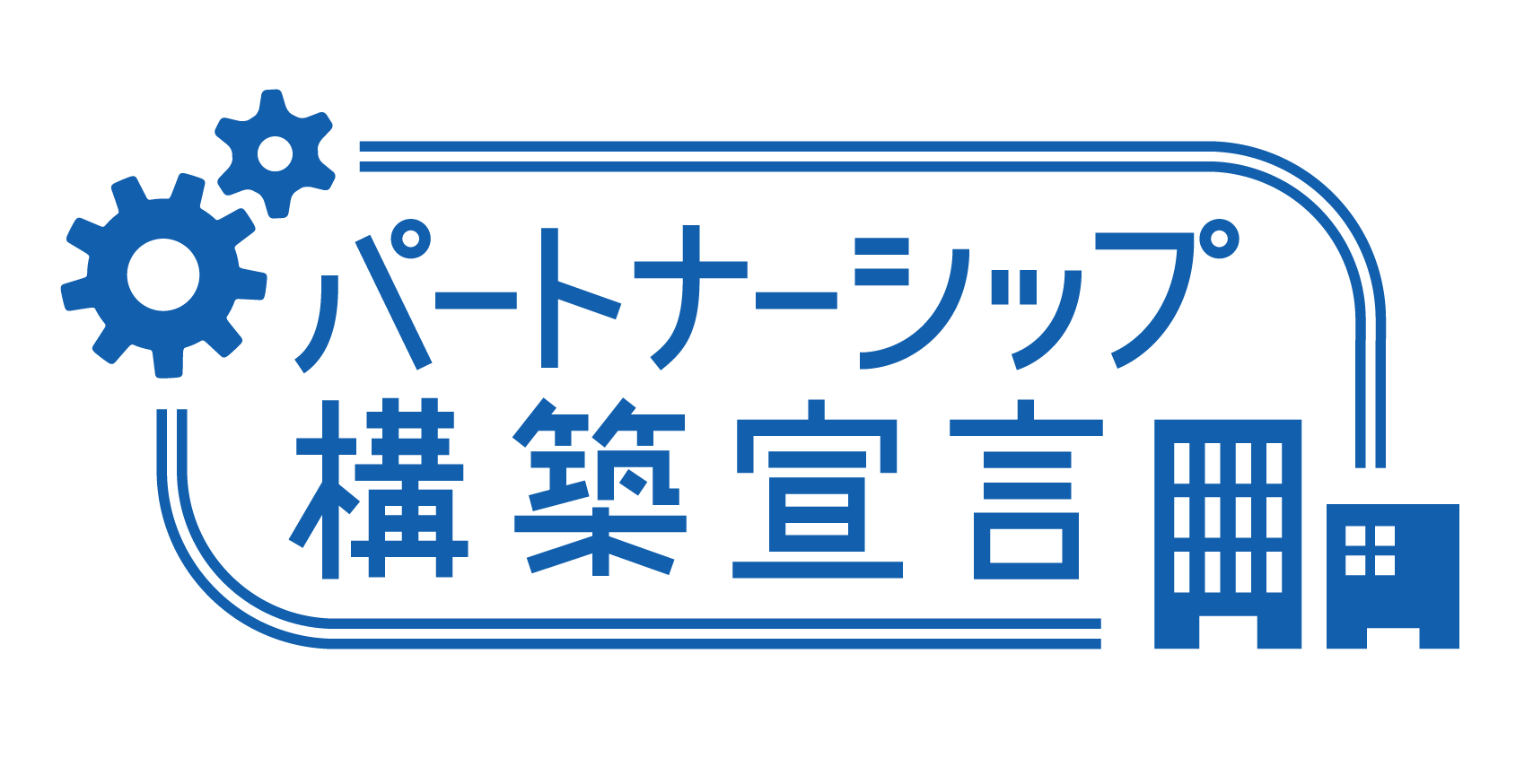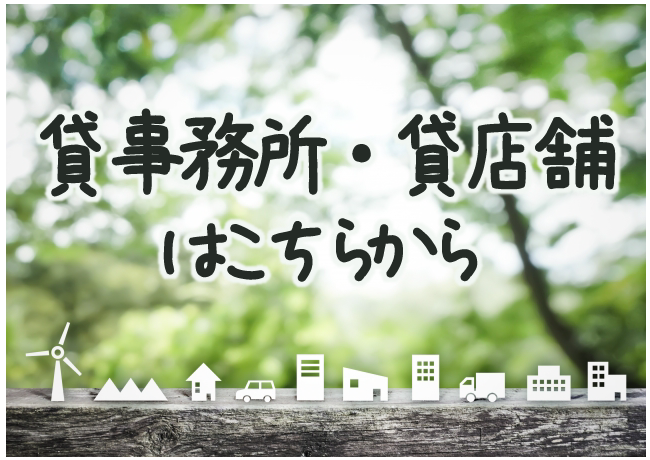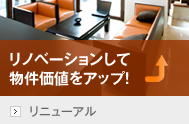[ 2025.2.1. ]
329号-2025.2
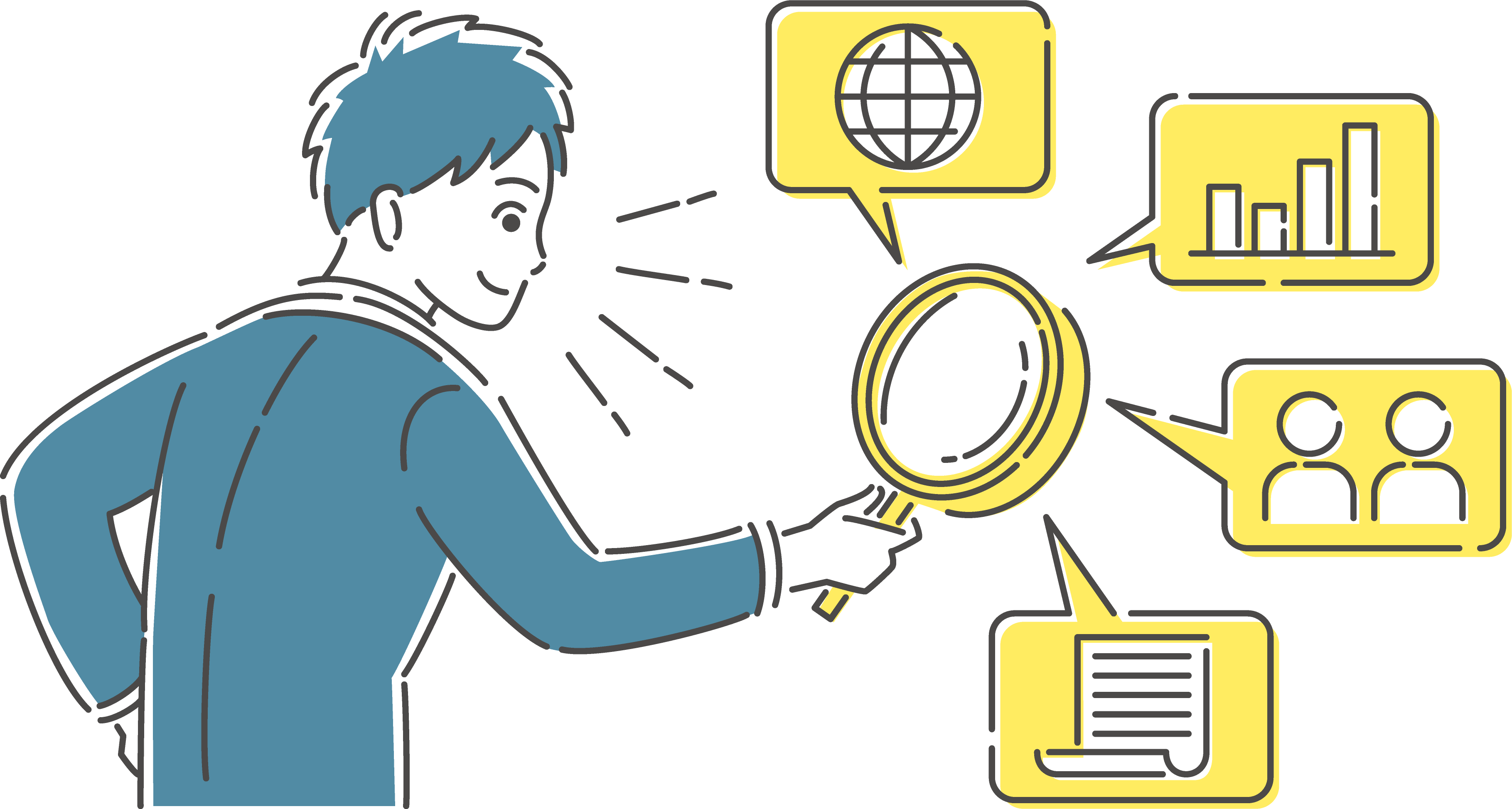
掲載期日と媒体は忘れたが、面白い記事が出ていた。
×年収300万円の人 ⇒ 家と会社の往復が基本的なパターンでいる。
○年収1億円の人 ⇒ とにかく寄り道する ⇒ 会いたい人や参加したいイベントがあれば新幹線や飛行機に乗っていく⇒長い休みが取れれば積極的に国境を越えて旅をする。
別に300万円の人が悪いとか、家と会社の往復の人生が可哀相だとか言いたい訳ではないが、移動距離と収入にある程度の相関関係があるそうだ。確かに高所得の人は活動的だし、全てにエネルギッシュで挑戦的だ。これは、比較の対象が増えたからではないかと考えられる。見聞きする情報量が格段に増えたからだ。しかも、それを嬉々として面白がる傾向がある。凄いのはそれを試そうとすることだ。
積極的に移動距離を伸ばすことで人は違った価値感、発想、人脈に出会うことができる。
そしてそれを今までの自分の知識と経験と比較できるので、大きなビジネスチャンスを物にできる確率が高まるのだろう。セブンイレブンも創業者の鈴木敏文氏が米国視察でサウスランド社のコンビニを見てライセンス契約を結び、1974年日本に一号店を作ったのもそうだ。鋭いひらめきがあったのも理由だが、日本にはなかった新しい形態を導入したのは英断に近い。
「日本は本当に良い国だな」と日本の良さを再発見できるのも、海外にいるときの方が圧倒的に多い。
海外旅行から帰国して、改めて日本の良さを再確認するという経験もあるはずだ。
結局のところ、人間のアイデアや閃きというものは脳にインプットされた、バラエティーに富んだデータから生まれて来る!ということになる。
勿論、アイデアだけでなく、それを現実的な形にするという実行力がポイントになる。
もう一つ改めて感じることがある。時間を支配している人も高収入?ということだ。
世界的に有名なビジネスマンは、声をかければ普通に海外視察に来るし、思い立つとすぐに海外の目的地に飛べる!ということは「自分の時間を完全に支配できている!」ということだ。
別に海外視察に限らず、この人達は日本にいる時から些細なことでもそうしている。
例えば、何かの懇親会を開催するときなどは、彼らは10分前ぐらいには、ほぼ勢ぞろいで、巷でよくありがちな、「すみませ~ん、仕事の都合で遅れますぅ~」「電車が遅延したので遅れますぅ~」「顧客から急の仕事を頼まれて行けなくなりましたぁ~」なんて言い訳をする人はいない。
もちろん神様はこの人達にも、上記のような懇親会に遅れたり、ドタキャンせざる得ないような試練を等しく与えているはずだ。でも毎回、難なくその試練を乗り越えて10分前には勢ぞろいなのだ。
超高級ホテルレストランでの懇親会で、開始時間丁度に到着したら、皆さんすでに円卓に「ズラッ!!」と勢ぞろいされていて、ものすごく気まずい思いをした経験はないだろうか?。私自身もある有名なチェーン店のオーナーとの面談で交通渋滞で10分遅れたことがある。
当然、その時間には会ってもらえず、2時間待たされた挙句、強烈な叱責を受けた事がある。曰く「君は私の時間を奪った!10分のロスを幾らか知っているか!」「その補填が可能なほど君の提案は価値があるのか!」と言われ赤面したことがある。その方はアイビーリーグを卒業されアメリカナイズされた紳士だったので、結果的に面談はしていただいたが、生涯肝に銘じる出来事と今でも心に刻んでいる。
以後は車の場合は30分前、公共機関を利用する場合は、約束時間の15分前には到着するよう心掛けている。これもビジネスの基本の一つだが、事前準備を欠かさない行動の一例だろう。仕事における事前準備の大切さを表す格言としてよく言われる「段取り八分、仕事二分」の心がけだ。

例のチェーン店のオーナーのように「自分の時間を完全に支配できている!」というのは、そういう高い次元での「自分のあり方」を言うのではないか。だから他人にも厳しい要求をするのだろう。人間には24時間、平等に与えられているが、要はその使い方次第で雲泥の差が付くという事になる。
その働き方も秒刻みで動いているから、時間コスト意識が並の人間よりも明確なのだろう。約束の時間に遅れるという事は彼にとっては「時間泥棒」に近いかもしれない。時間という無形資産を奪ったに等しいからだ。
よくあるのは、顧客と約束した資料の提出期日に「きちんとした期日」を言わない事がある。曰く「今週中に提出します」ひどいのになると「近いうちに提出します」だ。これは顧客のストレスは想像に絶する。言っている本人は気にしないだろうが、顧客の信頼を失墜させる事は間違いがないし、ビジネスにも影響は大きい。
それに関連して「時間貧困」という事がある。週全体の時間から、睡眠や食事など基礎的な活動の時間と家事や育児など生活に最低限必要な時間を差し引き、さらに労働や通勤に要する時間を差し引いたものを裁量時間と呼ぶ。これがマイナスになる場合「時間貧困」状態となる。これから脱するためにはムリ無駄を省くことが必要で、その剰余時間を自己の生産性や知識の習得に充てる事が必要になる。その積み重ねが人生の勝者になるポイントだ。時間を有効に使うという事は、様々な情報をいかに沢山消化するという事に他ならない。勿論情報の洪水に流されないためには、取捨選択が必要だがこれも今までの経験がものをいう。
所得格差の例ではなく、我々の日常行動でも同様なことが言われる。
営業活動にあっても、同じパターンを無意識にとっていることがある。
営業車で顧客回りをする場合でも、通勤する場合でも同じルートをとっていることが多い。ルートを変えれば競合先の動きにぶつかる事や空き地だった土地やアパートがいつの間にか他社で建築されていたり、競合先の不動産会社の看板がつけられていたりすることがある。それを元に自分の営業活動を変えたりする契機になる場合も多い。通勤途中でもいつも乗り降りする駅ではなく、一つ前の駅で乗り降りする事で、今までにない経験をすることがある。定型的な行動パターンを意識的に変えることが必要だという事になる。社内業務でも同じだ。慣習的前例的な作業を何の疑問も持たず坦々と処理している社員も多いが、ちょっと違う角度から業務を見直すとかで、意外とムリ無駄がはっきりとする場合がある。
仕事を改善するうえで重要なことは、この仕事の目的は何かと考える習慣にしておく。改善とは目的と手段の最適化である。つまり仕事の目的を達成するために最適な手段をとる事である。
ある高層ホテルでは開業当初、宿泊客から「エレベーターが遅い」というクレームが相次いでいた。社内の対策会議において施設技術チームからは「高層階用と低層階用に分ける」「スピードが速いモーターに変える」「エレベーターを増設する」などの案が出された。しかし、このホテルでは「各層のエレベーターホールに鏡を設置する」という対策を打ち出し、クレームを減らすことに成功した。このケースはエレベーターを待っている間、手持ち無沙汰にしないという点に手を打ったのだ。1分間の待ち時間で「手持無沙汰で待つ」のと「鏡の前で身だしなみを整えながら待つ」のでは
感じ方が違うと考え、スピーディーにかつ低コストの対応をした。この問題を広い視野で見て、エレベーターそのものではなく、顧客の心理という側面に着目した事で問題解決の手段にたどり着いたのだ。
見方を変えるという視点は様々なシーンで活用でき硬直化した我が国の労働市場でもダイバーシティとか女性の役員数などが注目されている。様々な考え方の人たちが在籍し、様々な視点で経営の方向性を考えるのは、30年に及ぶ停滞した日本経済の活性化対策には正解だが、日本経営の特異性である稟議制度から言えば益々結論が出ない事態も予想されるマイナス面も危惧される。いずれにしてもリーダーシップの問題に突き当たるが、経営コンサルタントや経営学者は次々と欧米の経営ノウハウを薦めるが、直接導入しても、国民性や企業風土から言っても中々難しいし、成功した例も寡聞にして知らない。
アーバン企画開発グループ相談役/合同会社ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之