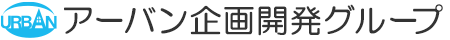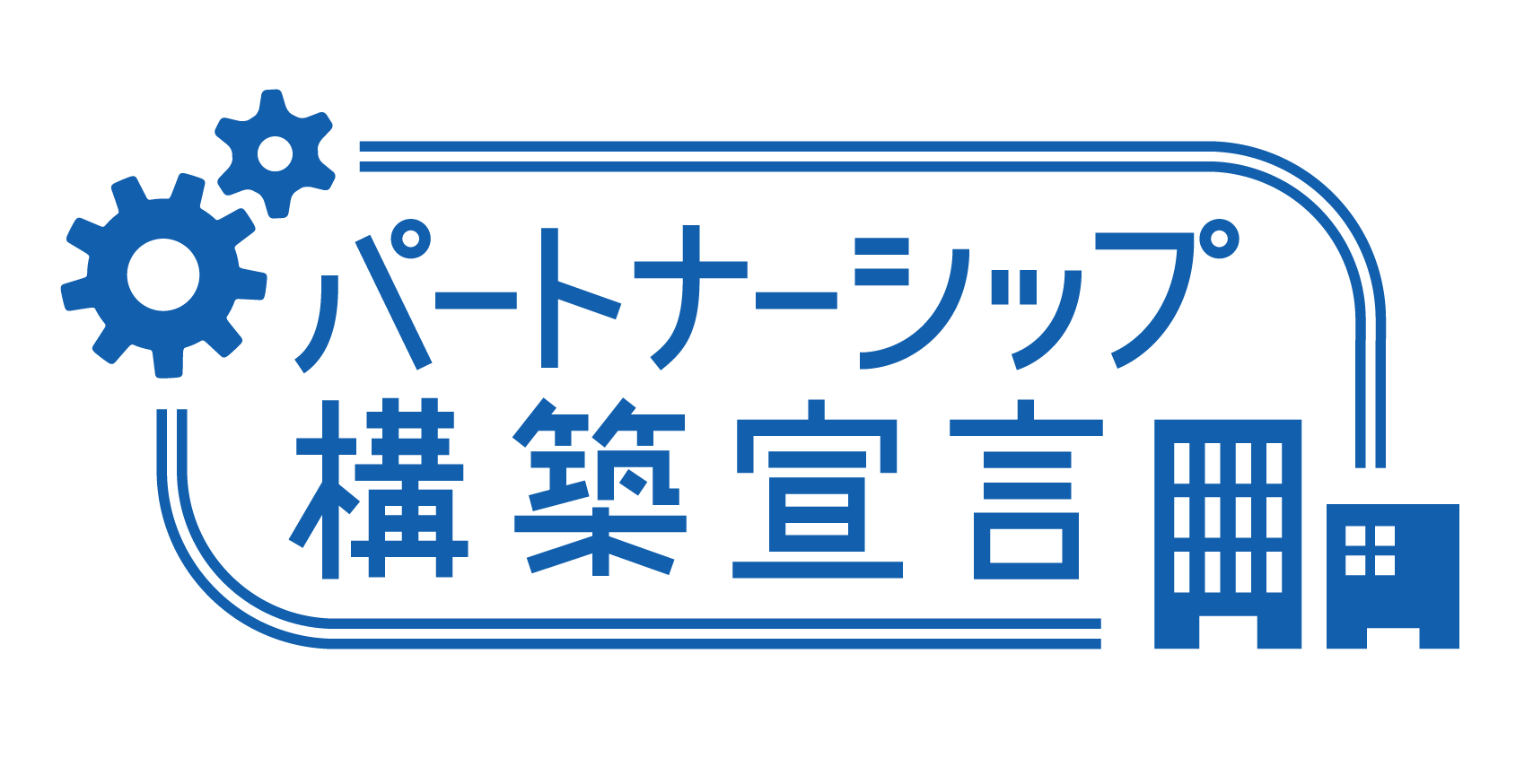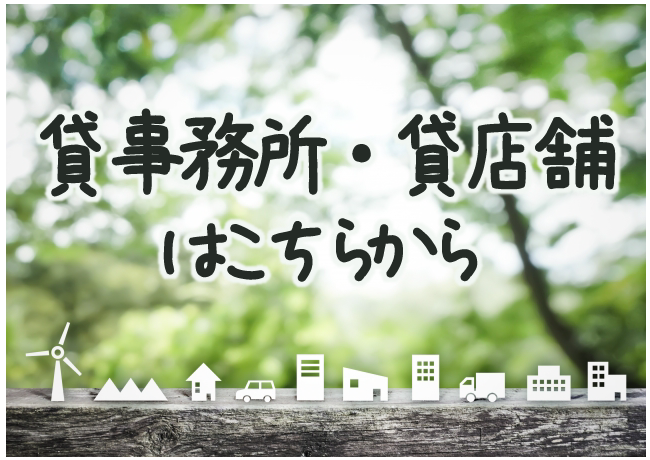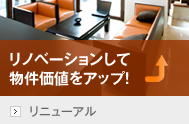[ 2025.4.1. ]
331号-2025.4
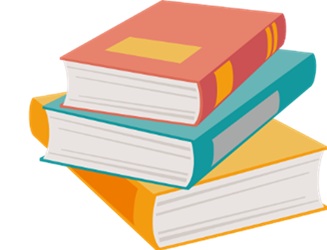 当社では、大卒新入社員の初期研修として、自己診断のために「日本語検定3級:高卒レベル」と「開成中学を含む難関中学入試の読解力問題」を課している。不合格者には「読売新聞社説」を150字以内にまとめる訓練を6ヶ月間行う。例年、新卒の試験結果は40%が不合格となる。
当社では、大卒新入社員の初期研修として、自己診断のために「日本語検定3級:高卒レベル」と「開成中学を含む難関中学入試の読解力問題」を課している。不合格者には「読売新聞社説」を150字以内にまとめる訓練を6ヶ月間行う。例年、新卒の試験結果は40%が不合格となる。
実施理由はコミュニケーション能力の向上だ。「相手が何を言っているのか」を正確に読み取ることができなければ、顧客との間で齟齬が発生し、トラブルになる可能性があるからだ。そのためには、ヒアリング能力と読解力を鍛えなければならない。我々のような中小企業がそこまでやらなければならないのかという疑問もあるが、顧客からの信頼を得るためには、それなりの手間暇をかけるしかないのが実情だ。
現在の教育行政にも不満はあるが、日本語の読解力の低下、および語彙の少なさは放置できない。平成の若者の基本的なビジネススキルの低下を憂えて久しいが、その原因は教育手法の問題に加え、読書不足とアウトプットの機会の少なさにあると言われている。
2023年11月6日に全国学校図書館協議会(全国SLA)が発表した「第68回学校読書調査」によると、2023年5月の一ヶ月間の平均読書冊数は小学生が12.6冊、中学生が5.5冊、高校生が1.9冊であり、不読者(5月一ヶ月間に読んだ本が0冊の児童生徒)の割合は、小学生7.0%、中学生が13.1%、高校生が43.5%となっている。残念なことに、当該月はGWがあり比較的時間が取れる月にもかかわらず、このような結果だ。大学生協による調査では、平均読書時間は22.2分で、「0」分が53.5%に上るという驚愕の結果が出ている。つまり、年齢を重ねるごとに読書量が減るという結果だ。読書量が減れば、当然アウトプットの機会も減る。
平均的なタイムスケジュールを見ると、18:00退社、19:00帰宅、食事や入浴、テレビに3時間費やし22:00、スマートフォンでYouTubeやFacebookを1時間見て24:00就寝、07:00起床となれば、読書をする時間を作るのは不可能に近いだろう。どこかで時間を作ろうとすれば、それぞれの時間を削るしかないが、現代の若者は誘惑が多く、よほどの自制心がないと難しいだろう。
となると、選択肢は2つしかない。通常の倍の記憶力と理解力がある社員を採用するか、強制的に会社側で時間管理をするかだ。どちらも中小企業には現実的ではないが、長期的な視点で見守るしかないだろう。ギフテッドと言われる知能指数130以上の、ずば抜けた知能の持ち主(ビル・ゲイツ、脳科学者の中野信子など)なら問題はないかもしれないが、それは望むべくもない。
人に教えるには言語化が必要であり、自分が理解できていることを他者がそのまま理解してくれるとは限らない。相手のレベルや状況に応じて、伝え方を適宜変えていく必要がある。そのためには、正確な知識と応用力、豊富な語彙が求められ、それらを体得することで自己のスキルは飛躍的に向上するはずだ。
会社が人材育成に投資するのは、あくまで社員の成長を通して、会社の業績向上につなげるためだ。社員は経営者が期待している通りには動かないことを前提に、より効果のある方法に取り組む必要がある。周りにはその問題解決方法として様々なノウハウ本があるが、目標設定の重要さを説いている。それも与えられたものではなく、自ら真剣に考えて作成したものでなければ意味がない。上司は目標設定について言及するのではなく、根本的な原因を自覚させ、そのアドバイスをもとに変革を促した方が効果は高いだろう。習慣化させることが重要だ。ましてや、今はハラスメントが問題視される時代であり、強制はできない。
「毎日の習慣が自分を作る」しかし、それを日常的に意識している人は少ない。「明日から」「来週から」などと先延ばしにする癖はないだろうか。「来週から」と51回言えば一年が経ってしまう。習慣化とはルーティンのことで、外圧的、内圧的にやらざるを得ない状況を作ることだ。場所が自動的に設定されるとか、やらないと落ち着かないとか、そういった状況を作り出すことが重要だ。
現状の若者の過ごし方を見ると、・テレビゲーム…26% ・楽器…21% ・スポーツ…18% ・教育…4% ・知的専門書…1%というデータがある。プリンストン大学のマクナマラ准教授らのグループが「練習量の多少によってパフォーマンスの差を説明できる度合」について研究した結果だ(「ニュータイプの時代」ダイヤモンド社参照)。つまり、音楽やスポーツの分野では「努力は報われる」という原則が18%以上当てはまるけれど、会社の仕事など知的専門職の分野では数パーセントと「努力は必ずしも報われる訳ではない」という研究結果だ。
オリンピックを見て、やはり「努力は報われる」と感じ、「さらに努力しよう」と決意を新たにした人もいるかもしれない。一方で、「努力は報われる」というのは必ずしもすべての領域に当てはまる訳ではないことを認識する人もいるだろう。周りを見ていて「あいつより自分の方が頑張っているのに、なぜあいつの方が儲かっているのだろう?」と思ったことはないだろうか?
この場合、「努力は報われる」という教えを忠実に守ろうとすると、「もっと頑張らないとダメだ」とさらに努力を重ねる。けれども、仕事の場合、努力の方向性ややり方が間違っていると、努力は報われないことが多いのだ。例えば、自分の見込み客になる人がFacebookをほとんど使っていないのに、毎日Facebookに投稿したり、お金をかけてFacebook広告を出すという努力を重ねても、売上を上げるという成果にはつながらない。
この場合、ビジネスで成功している人が「これからはFacebookをやらないとダメだ」といくら主張しても、その教え通りに努力することは、努力する場所が間違っていることになる。
単に努力する場所が間違っているケースは、努力する場所を変えることで問題解決につながる。また、努力する順番が間違っているケースもある。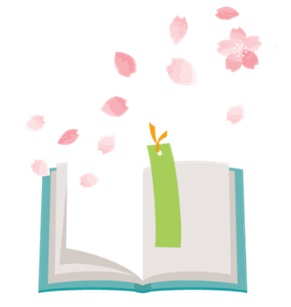
例えば「ホームページを充実させないとダメだ」と考えて、お金をかけて立派なホームページを製作している場合。もちろん、ホームページはあった方がベターだが、「ホームページで何をしたいのか」という目的を決めないまま、業者の言いなりで作ってしまうと、見た目も綺麗で立派なホームページはできたけれど、肝心の問い合わせが全然来ない状況に陥る。巷間言われる「努力は報われるという命題」はミスリーディングとなる可能性があるのだ。
普段人一倍頑張っている努力家の人にとっては、自分を否定されているようで素直には受け入れがたい意見かもしれない。しかしながら、自分は努力を重ねているのに、思ったような成果を手にできていないと日頃感じているなら、さらに努力を重ねる前に「いまの努力は本当に報われるのだろうか?」とちょっと立ち止まって考えることで、現状を大きく変えられる可能性がある。
なお、一生懸命頑張っているのに、満足のいく結果が得られていない場合、感情と思考のねじれが原因ということもあり得る。仕事の場合、努力する方向性ややり方が違うと、努力は必ずしも報われる訳ではないことを自覚することが必要になる。そこでリーダーの力量が問われる。精神的なサポートと報告、連絡、相談だ。当事者に共創するという意識がないと、的外れなプレゼンになり、顧客の信頼は失われるだろう。一人一人が会社の看板を背負っているという感覚があれば「チームとしての強み」が発揮でき、より強固な関係が構築されるはずだ。
アーバン企画開発グループ相談役/合同会社ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之