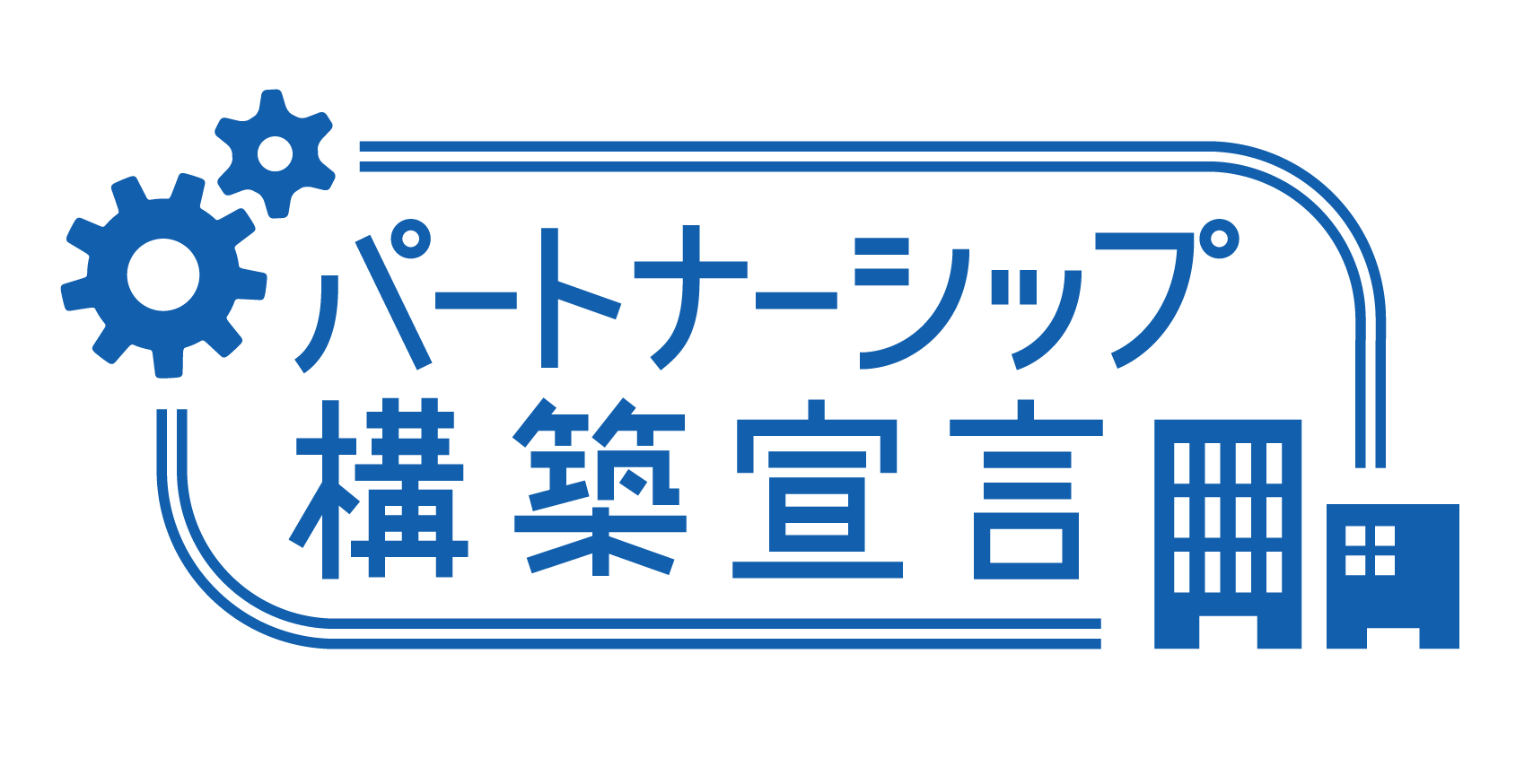[ 2012.3.29. ]
176号-2012.3.25
 12月の賞与の時期がやっと過ぎた。「賞与は果たして必要なのだろうか」と悩む時期でもある。生活給といわれ「当然支給される権利がある」という風潮が疑問なのだ。社員の募集条件欄でも「賞与○ヶ月」と書く事になっている。残業時間もそうだ。そこには成果に対するという視点が欠落している。全ての社員の能力は一律でもなく成果を生み出す時間も結果も異なるからだ。それから言えば事前に確約することはできない。
12月の賞与の時期がやっと過ぎた。「賞与は果たして必要なのだろうか」と悩む時期でもある。生活給といわれ「当然支給される権利がある」という風潮が疑問なのだ。社員の募集条件欄でも「賞与○ヶ月」と書く事になっている。残業時間もそうだ。そこには成果に対するという視点が欠落している。全ての社員の能力は一律でもなく成果を生み出す時間も結果も異なるからだ。それから言えば事前に確約することはできない。
賞与がなぜ7月と12月なのかも確たる理由がない。日本では古くは江戸時代に商人がお盆と年末に奉公人に配った「仕着」が由来と言われている。第二次世界大戦敗戦後のインフレーションで労働運動が高揚し、生活のための出費がかさむ夏と冬に生活保障的な「一時金」としての性格を帯びるようになり、毎月の給与のほかに賞与として定着したらしい。賞与の意味と性格も変わっているが「既得権」「慣習」というものは何時の時代もなかなか改変できないものだ。
バブル崩壊後、終身雇用制度と年齢給が見直され、成果主義が取り入れられると同時に、年俸制や生活給としていた賞与も業績連動型に変容してきた。月額給与の構成部分にも年齢給的な要素が少なくなり成果給的な部分が多くなると、当然賞与にも反映されてくる。この発展系が年俸制度かもしれない。業績連動型の賞与が実質年収の半分を占めてくると、年俸制へ近づくので、現在の給与体系は過渡的制度と位置づけられる。
先進的な企業では、賞与は完全に業績連動型になり社員個人毎に支給額も0~数百万となるようになった。業績が右肩上がりだと年2回の賞与の支払いも負担にならないし、大盤振る舞いもできる。場合によっては年3回も可能だ。税金に取られる事より、その分を社員に支払った方がいいと自ら言い訳がつく。社長以下の経営幹部やその従業員も毎年支給するパイが大きくなるわけで、不満が出ても来年へと希望をつながせることも可能だ。
社員も「来年頑張ればいいや」と多少の不満があっても収まるし、他社と比べそれなりの支給が確保されていれば納得する。支給側は面倒な考課をせずに「ドンブリ勘定」で済む事になる。
しかし、景気が右肩下がりか横這いになると、早々ドンブリ勘定もできなくなってきた。パイが限られてきたからだ。限られた少ないパイで、貢献した社員、頑張ったけれど成果がなかった社員、満足度は低いがまあまあの社員、の処遇を公平に考えなくてはならなくなった。「処遇の公平」とは支給額に差をつけることだ。
大体不満を持つのは、業績が中堅クラスの社員である。
上位クラスと下位クラスは意外と不満が少ない。ここで言う上位クラス、下位クラスは社員全体の5%、他は中位クラスである。上位に近い層から下位に近い層まで幅広いから問題も複雑になる。中でもその層の上位層が不満を持ちやすいし、組織的にも中堅層に位置するからその客観的評価に頭を悩ますことになる。
今まで様々な評価基準を作成し、改定してきた。人事コンサルタント会社主催のセミナーにも何回となく出席してきた。関連の書物も何冊も読んだ。「社員全員が納得する客観的基準が必要だ!それも見える化すべきだ」「相対評価、公平さがないとモチベーションが下がる」等々と誰でも納得する内容だ。様々な解析手法やデータに基づく評価マニュアルも見た。しかし、不思議なのは個人個人の支給額を社内公表するものは一つもなかった点だ。
社員が明確に理解できる「相対的評価」ではなく、実質は自分だけの「絶対評価」なのだ。
基準はあっても社内の他人と比べることはできないのだ。勿論、ネットで自分の年齢相当の年収や賞与額は簡単に分かるが、具体的基準が自分と比較できないので結果的に効果が少ない。それに公表しているのは、全て人材派遣や転職奨励会社なので全面的には受け取れない。
「雇用の流動化」が、停滞した日本経済の活性化に資すると官民上げて吹聴した。しかも終身雇用制度、年齢給が、高齢者を優遇し若年層の雇用の障碍とまで言い切った。バブル破綻のつい数年前までは、それが日本経済の躍進の下であり世界に画する制度となっていたのにである。
それがバブル破綻後、失われた10年どころか20年にもなろうとする低迷した経済状況で、格好の理由付けを見つけたのだ。自分の価値を見つめなおし、次のステップへ飛躍するように煽ったのだ。最近では「自分探し」というキーワードもそうだ。さらに「幸せ度」「絆」も加わった。
「雇用の流動化」は「解雇規制の緩和」「ライフ&バランス」のセットがついていた。だから当時は正規雇用者を護るという観点から反故にされたのだ。その結果はどうだったか?今度は少子高齢化を踏まえて「生産年齢人口の減少」が危惧され始めてきた。そうすれば新たな「国家総動員体制」が必要になってきた。つまり、女性の就労動員、非正社員の雇用促進、年金財源不足問題と絡めた65歳定年延長制度の義務化である。国民総生産の低下、経済成長率低下が護摩札のように危機感を募らせてきた。国債発行残高の際限ない膨張の元に国内金融資産で担保の懸念が出て財政破綻がより現実のものになった。野田政権による2015年からの消費税10%の導入も国債の満期返済と利払いで吹っ飛び、国家財政の破綻は避けられない。そもそも現在のデフレ原因が労働生産性の頭打ちと人口減少なので、高コスト体質になった人件費の削減、外国人就労規制の緩和と機械化の促進、製品の高付加価値が求められている。
わが業界に置き換えれば、「誰にでもできる仕事:すぐ代替が利く仕事」「少しトレーニングと知識がないとできない仕事」「あなたしかできない仕事」で給与や待遇差が明確に出てくることになるし、それが他社との差別化にもなる。欲しいのは当然「あたしかできない仕事」をする社員だけだ。「人罪」「人在」「人材」「人財」の区分もある。その区分は時代の進歩と消費者の要求により動くということで、「人材⇔人在⇔人罪⇔人財」に変化する厳しいものだ。
「人が全てだ」という有名なGE(ゼネラルエレクトリック)の信念がある。GEのリーダーシップ研修は世界最高レベルといわれ、人の強さが会社の強さになっていると賞賛された。
しかし、GEの人事制度は「社員をトップ20%、ミドル70%、ボトム10%にランク別けし、ボトム10%を解雇する厳しいものだ。「透明性の高い組織で明確な業績目標とその評価制度が整っていれば、ボトム10%の人は自分がどのようなポジションにいるのかわきまえているはずだ。たいていの人は、言われる前に自分から辞めていく。自分が必要とされていない組織にいたいという人はいない」と明快だ。ボトム10%の人に「優しい会社は」はそんなに頑張らなくてもいいというメッセージを発して本当にやる気のある人を腐らせていると判断している事になる。そしてその評価を率直に本人に知らせるのがGEの流儀だそうだ。
よくしたもので「甘い会社」には「甘い社員」が集まり、その社員がよく言う「仕事にやりがいが無い」と感じるのは、自分がそれを求めているかもしれない。全てにあいまいな幼児化する日本社会で「時間を惜しんで成果を出せ」「一人ひとりが社長の代理だ」「給与も自分で稼ぎ出せ」はパワハラの誹りを逃れない。中小企業に精神的財政的余裕はないが、倒産リスクは社員も負ってくれるのか、ないのならどうしても腑に落ちない。
社長 三戸部啓之