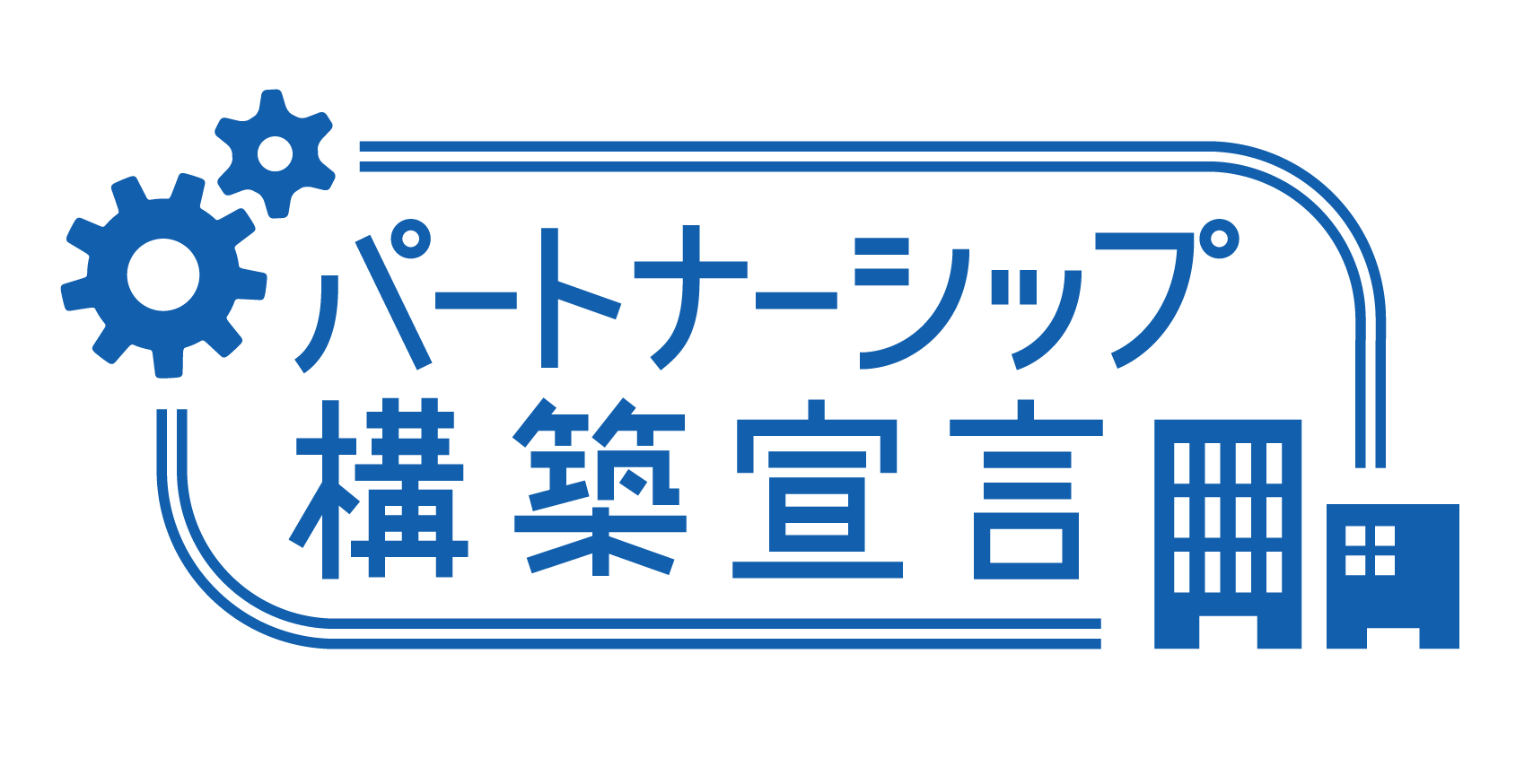[ 2018.12.1. ]
257号-2018.12.25

「貸してください」→「貸しましょう」、「嘘ついて借りた人」→「騙されて貸した人」どちらが被害者なのか? 「借りた人」が「貸してくれた人」を刑事告発した。
更に貸し手自体がそれを知っていて黙認したというおまけまでついている。こうなると益々どちらが被害者か判断が難しくなる。こういう点の追求はマスコミの真骨頂だ。全国紙をはじめ各紙がスルガの企業体質まで言い始め、借り手責任を転嫁しだした。消費者ならば消費者契約法に守られて当然だが、ただそれが借金不動産投資でも?妥当なのか!投資用ワンルームマンションを一つ買い、それでも足りず、2つを買ってから「私は消費者だから守られるべき」と訴えを認めた東京地裁の裁判官がいる。「非現実的なシミュレーションを提示、月々の小遣いで賄えると誤信させた・・・」から消費者契約法による取り消しは・・・との理由なようだ。
非現実的シミュレーションを信じるようなアホ投資家は事業者ではなく消費者だから、救うのは当然という見解なようだ。
売主の不動産会社が破産になれば消費者契約法の取り消しでは救えない。被害者を救うためには、金持ち加害者「スルガ銀行」を血祭りにあげるしかない。株式会社にノルマは当然だが銀行は公的機関だからという訳でご法度らしい。しかもその粗探しゴールが創業者一族が経営権を握っていると炙り出し、その独裁的な経営体質を問題にするわけだ。まして数年前は地銀の優良経営と金融庁が認めた会社だ。その舌の根も乾かない内に一種のイメージ操作をしだした。マスコミによる世論誘導で事の原因を作った『欲』を希薄にしたから、社会的弱者=善人救済の図式になりつつある。
最近の被害事件はすぐ、「被害者の会」等による被害者争奪戦が始まる。被害者救済ダイレクトメールも飛び交い、弁護士にとってビッグなビジネスチャンスだ。総額2000億円といわれる規模から弁護士の手数料10%(着手金+成功報酬)200億円にもなる。米国でいう「アンビュランス・チェイサー」だ。
米国では交通事故にあうと一番先に駆けつけるのは救急車より弁護士で、被害者にすぐ名刺を渡し訴訟代理権を受託する弁護士のジョークだが、日本でも最難関の司法試験の合格者の政策的増員から「食えない弁護士」が増えている。一般的に彼らは司法修習終了後、「居候弁護士」を数年経て独立したわけだが、資格者が激増したため法律事務所に採用されることもなく、フルコミッションで法律事務所の名前を借りる「軒先弁護士」が数年前まで一般的になった。近年それも少なくなり、実務も知らずに自宅で独立する「即独弁護士」、数人で事務所を借りて始める「相部屋弁護士」も多い。このような弁護士の為に「法テラス」があるが、それも待機弁護士が多く中々順番が回ってこない現状がある。訴訟事件も少ないから自ら訴訟を仕掛けるとかしないと食べていけない。おお威張りで他人の金を預かる事ができる弁護士は、金銭のつまみ食いの誘惑に晒されている。勝訴や和解になっても被告側から振り込まれる金員が代理権を持つ弁護士の口座に先ず最初に入るのも、その誘惑に拍車をかけている。勿論それだけでなく、成功報酬のとりっぱぐれを防止するためにも有効だから自分の口座に振り込ませる弁護士が多い。日本弁護士連合会によると、非弁提携を含む懲戒処分件数は1997年の38件から、2017年は106件まで増加。弁護士自体の刑事事件発生率も法務省と警察庁の統計によると詐欺は人口10万人当たり0.5人、横領は0.6人で一般の犯罪率よりも高い異常事態になっている。法務省によると、2017年の弁護士数は約3万9千人で、20年前の2~3倍に増加。
一方、弁護士白書によると、仕事を始めて5年未満の弁護士の平均年収は2006年1613万円だったが、2014年は796万円に減少。2015年に弁護士1年目だった人のうち年収400万円未満だった割合は16%に上るという調査もある。
刑事訴訟法が改正されて被害者本人ではなく第三者が訴訟を提起できる事になったから、弁護士も訴訟勧誘にビジネスチャンスを見出している。だから昨今、従来の日本的慣習であった「話せばわかる!」ではなく「すぐ裁判で決着をつけよう!」となっているのも、弁護士に相談するのがそれだけ身近になったという事だ。つい先日も弊社が管理している駐車場に不法駐車があった、その利用者である契約者が数日間駐車できなかったので、契約解除を通知してきた。さらに、仲介手数料の返還と数日間の使用できない事による損害賠償として数万円の返還請求が弁護士名で弊社に内容証明で送られてきた。以前ならまずこんな事で起こる事案ではないが、一寸したトラブルでも弁護士が介入してくる時代になった。話がわき道にそれたが、先のスルガ問題は、バブル崩壊後に流行った言葉「貸し手責任:レンダー・ライアビリティー」貸した側も悪いという論理だ。見方を変えればいつも最終責任は「お金持ち」がとる事になる。取れるところから取るのが、ビジネスの常道だ。理由は後付けでいくらでも可能だ。今回のように数の論理で押し切れば正義になる。愚民化した社会では民主主義の正義の概念はどの様にも変わる。民主主義の主要な前提である自己責任はどこへ行ったのか?一定の責任能力と行為能力を持った人間を法が無能と認定しているようなものだが、マスコミもそこは目をつぶる。難しい法理論はさておき「我欲」を法的正義、社会的弱者のもとに救済する。消費者契約法を今一度整理してみよう。
消費者と事業者とが交わすすべての契約で、虚偽説明や不適切勧誘があった場合に契約を取り消せるルールを定めた法律。平成12年法律第61号。2000年(平成12)に成立し、2001年4月に施行された。事業者のもつ情報の質・量や交渉力が消費者より圧倒的にまさっている状況を踏まえ、悪徳商法だけでなく、消費者に不利な商慣行などから消費者の利益を守る目的がある。事業者の損害賠償責任を免除する条項や消費者の利益を不当に害する条項を無効とすることも可能である。
2007年6月には改正消費者契約法が施行され、消費者にかわって、内閣総理大臣が認定した消費者団体(適格消費者団体)が事業者の不当行為を差止め請求できる消費者団体訴訟制度を導入した。これまでに消費者契約法に基づき、大学合格時に納めた授業料の入学辞退者への返還、賃貸住宅の退去時に敷金や保証金の一部を無条件でとられる「敷引き」慣習の無効、「いつでも受講できる」と銘打っていた英会話学校の勧誘差止めなど、消費者に不利な慣習や不当契約を改善した事例は多い。その後、認知症や高齢で判断力が低下した人につけ込む悪質商法の被害が後を絶たないため、2017年には再度、改正消費者契約法を施行。高齢者に何十着もの着物を販売するなど、通常必要とされる量を大きく超えた物やサービスの売買契約(過量販売契約)を取り消せる規定を新設した。「床下にシロアリがいて家が倒壊する」といった契約上の重要事項で嘘の説明をする「不実告知」を受けた際も、契約を取り消せるよう重要事項の範囲を拡大した。不当勧誘行為があった場合、契約を取り消せる期間を半年から1年へ延長した。その期間は何時でも取引が無効になり、商取引は完結しない。取引の安全や履行責任という近代法の原則を無視し、国家による民事取引介入になっている。なお消費者契約法とは別に、訪問販売や電話勧誘などの取引手法に限定し、消費者保護を目的とする法律に特定商取引法がある。特定商取引法は、一定期間内の解約を認めたクーリング・オ
社長 三戸部 啓之